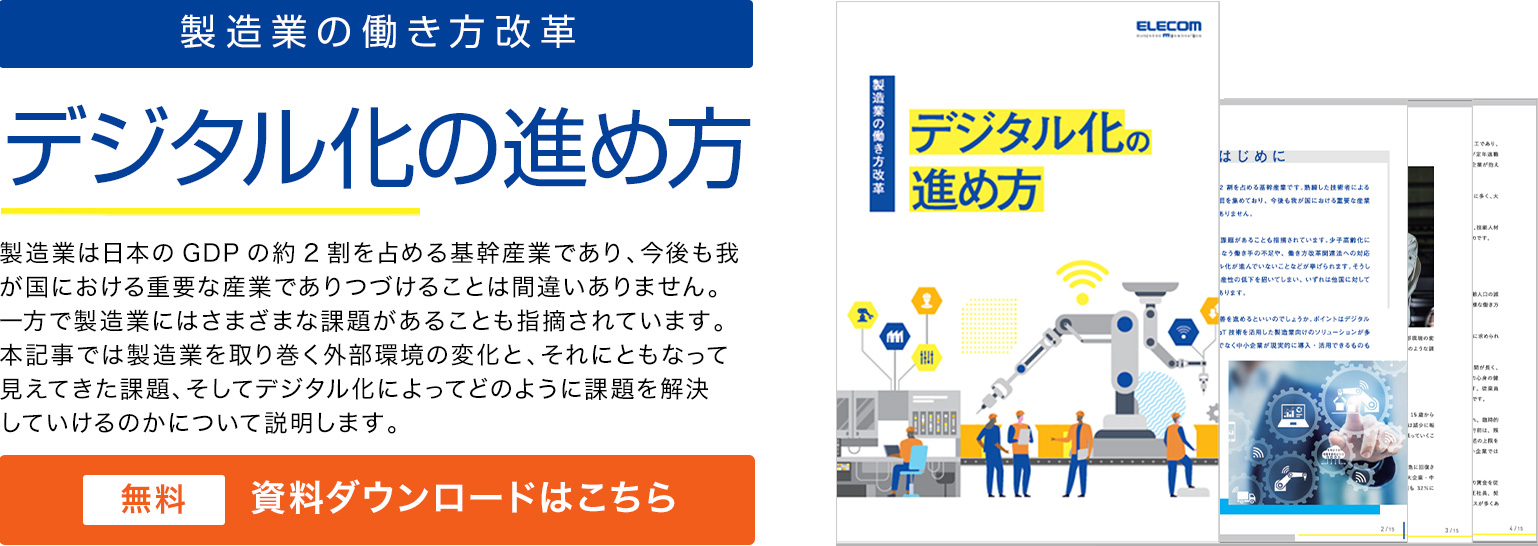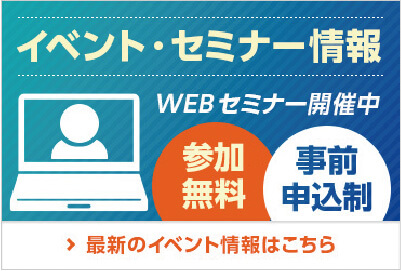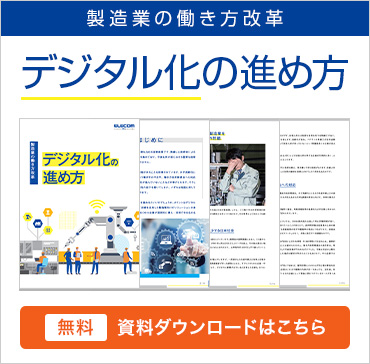【経済産業省】あと5年。2025年の崖を好機に変える企業とは・後編

経済産業省が『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』(以下、DXレポート)を発表してから1年半。
「レガシーシステムを使用し続ける企業は、損失だけではなく、海外や国内ベンチャーとの競争にすらならなくなる恐れがあります。」と語るのは、経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 ソフトウェア・情報サービス戦略室長 田辺雄史(たなべ・たけふみ)氏です。企業のDX化やデジタル技術の活用に警鐘を鳴らし続ける経済産業省へのインタビューを前後編の2回にわたってお届けします。
前編では、DXレポート策定の経緯や企業が2025年の崖から落ちた場合の行方についてお聞きしました。後編となる今回は、2025年の崖を乗り越える企業の特徴、2025年以降の企業戦略について語っていただきます。
囲い込みはもう古い? DX時代を勝ち抜く企業とは

DX・2025年の崖に危機感を抱いていても、現状のビジネスモデルや提供価値を変革するには大きな決断が必要になります。デジタル技術を活用した「勝てる企業」にはどのような特徴があるのでしょうか。
「マーケットの垣根をなくす」のがポイント
- 田辺氏:
- 先進的な企業というのは、従来の方法を前提としないゼロから考えるケースが多いと感じます。組織形態・ターゲット・主戦場にするマーケットをゼロベースで見直し、デジタルで組み直した時、従来提供している価値を疑って考えられる企業は非常にDX的です。
これまでのビジネスでは、自分たちのマーケット内の顧客が逃げないよう、囲い込みで戦略を練っていた企業が多かったと思います。しかし消費者ニーズの変化が激しいDX時代のビジネスは、「マーケットの垣根をなくす」のがポイントです。
マーケットの枠を広げ顧客とのタッチポイントを増やし、購買行動やニーズといった多様なデータを収集する仕組みを整えることが、付加価値の提供につながります。従来の固定観念で囲い込みを前提としたビジネスは、決して安泰ではありません。デジタル技術を活用したデータ収集と、他の企業よりも先んじて実施する決断力が求められます。既存のビジネスモデルから脱却し、自らマーケットを広げるという発想が重要です。
勝てる企業はビジネスをアップデートし続ける
- 田辺氏:
- 顧客の価値最大化を掲げるAmazonは、まさにDXの体現者で、常に新たな価値を他の企業よりも先に提供し続けていますよね。国内の例だと、トヨタが挙げられます。彼らは内燃機関の車で戦い続けることに危機感を持ち、電気自動車が脅威だと思っています。今はレガシーな内燃機関の車が売れているけど、どこかで電気自動車にシフトするのか、違う世界を作るのか、彼らの危機意識のレベルなら乗り越えられると思います。実際いろんなIT企業と組んでマーケット領域を拡大しているので、彼らのようにビジネスモデルをアップデートし続けている企業がDX時代も勝ち続ける企業になると思います。
中小企業のDXを進めるためには…

新しい提供価値を常に生み出し続けるとは言っても、資金やリソースの問題で新領域に挑戦できない中小企業は多いのではないでしょうか。既存事業を生かしながら企業のDXを進めるポイントや、具体的なビジネスモデルについて伺いました。
戦う場所の見極めが重要。企業の「共同化」とは
- 田辺氏:
- サプライチェーンの中にガチっと入ってしまっている中小企業は、既存ビジネスに忙殺されてしまい、自力で新規開拓やDXを進める余力がありません。そこでカギになるのが、企業同士がそれぞれ戦い合うのではなく、“共同の世界を創る”という考え方です。
例えば、京都には機械金属関連の中小企業10社が共同で立ち上げた「京都試作ネット」と呼ばれるWEBサイトがあります。ユーザーがWEBサイトの入力フォームやメールで製品試作を依頼すると、メンバー企業に内容が配信され、依頼内容に最適な企業が2時間以内に照会へ返信します。顧客の思いを素早く形に変える京都試作ネットを使用すれば、試作の段階から小ロットで最適な企業に依頼ができるため、的確かつスピーディーな製品開発が可能です。受注するメンバー企業も、本業の部品製作で多忙を極める中、多少の余剰を活用し試作製作を請け負えるため、その後のビジネス発展が期待できます。
中小企業におけるDXは、まず既存ビジネスを共同化などで圧縮し効率化、すなわち楽をすることで、余剰を生み出し、その分違うところにリソースを投入するのが重要だと思います。ライバルではあるが、勝負しなくてもいい場所を一緒にやるというアライアンスがひとつのカギです。それは中小企業にかかわらず、社会全体で意識し改善すべきポイントでもあります。
競争から共創へ
- 田辺氏:
-
2025年の崖を乗り越えた企業・社会では、囲い込みや自前主義ではなく、先ほども述べた共同化が進むと思います。レガシーなビジネスでコツコツと経営していても、いつかは革新的なテクノロジーでブレイクされてしまうので、戦わなくていい部分は手をつなぎましょうと。共同化の動きは世界でも進んでおり、前回のCES(毎年1月、ネバダ州ラスベガスで開催される電子機器の見本市)では、スマートスピーカーの領域においてApple・Google・Amazonが、音声での命令とそれに対して通信するプロトコルを提携し、ひとつの規格を開発する方針を発表しました。一方、今の日本の家電メーカーでは、それぞれが規格を提示して、周りが合わせるように誘導するやり方です。業界のシェアが取れているApple・Google・Amazonの3社で協力して生まれる製品とどちらが有利かという点で次の一手を考える必要があります。
もちろん共同化に至るまでには、先の例で言えば各社が熾烈な競争をして、結果としてこの3社が残り、あとは手をつなごうという結果になったのだと思います。しかし日本は殴り合いをやめないし、ライバル同士が手をつなぐことはあり得ない。キャッシュレス分野での〇〇payも同じです。ずっと殴り合いを続けていて、どこかが潰れるまで競い合っています。勝負がある程度見えてきた段階で共同化をし、違う部分で差別化をはかって勝負する、という見切りを日本企業は身につけていけたらいいですね。
2025年以降、日本が世界に勝つための方程式

世界のDXが進む中、未だDX化が遅れている日本企業。今後システムの刷新が完了し、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革が本格的に始まる2025年以降、日本企業の競争相手は世界中に広がります。グローバルで日本企業が勝つためのポイント・武器はどこにあるのか。「ものづくり」の視点からお話しいただきました。
国内・海外の垣根をなくした発想の転換
- 田辺氏:
- 日本の製造業は、世界的に見てかなり技術力が高いレベルにあります。しかし、たくさんものを売ればひとつが安くなるとか、あらゆる顧客に丁寧に対応する個別の開発とかは広がりに限界のある考え方です。ポイントは、デジタル技術を組み合わせてひとつのものを作り、みんなが使えるものにするといったやり方への発想の転換です。
従来のものづくりの考え方でグローバル市場を開拓する場合、物流や商社といった制約が発生します。しかしデジタル技術を活用したソフトウェアの場合、クラウドにのせ場所や距離に制約のない価値提供が可能です。もの売りでは難しい部分も、ソフトは一度作ってしまえば言語を変えて勝負ができます。国内・海外の垣根をなくし、新しいサービスを作っていくことが重要です。
日本のものづくり文化が強みになる
- 田辺氏:
- DX時代のものづくり文化で重要になるのは、専門的な技術や質の高いハード機器ではなく、製作物に関する技術・工程のデータになります。むしろハード機器を抱え、自社ですべてを製作するとなると、機器の管理費・メンテナンス費とコストが膨らみます。
例えば、伝統的な技術を持つ地方の町工場にNASAから部品製作の継続的な依頼があったとします。技術や工程がすべてデータ化された世界では、そのデータに価値が生まれ、対価が支払われる。受注したからアメリカで工作機械を買って固定資産税を払い工場も作って…ではなく、どこかのOEM企業に作ってもらい、部品を工作するノウハウといった知財を守った上で納品してもらうビジネスモデルになるでしょう。クラウドデータ上のやり取りは場所を問わず、設備さえあればいい。でも設備は自分たちで持つと管理するのが大変なので持たない。そうしたビジネスモデルになりえる企業は、ものづくりの世界にはたくさんあると思います。
日本で生産して外に売りにいくという、もの売りの商売で考えると、ハードルが高く厳しい。今まで日本の中で一所懸命作ってきたものを、デジタル技術の導入とビジネスモデルの変革でアライアンスを組めば、グローバルで売り出すには十分なチャンスになります。そこに日本が持つ「ものづくり」の勝ち筋があるような気がします。
経済産業省のDX

最後に、経済産業省内で進めているDXについてお話を伺いました。
- 田辺氏:
- インフラとしてはノートパソコンを導入し、テレワークなど場所を選ばない業務が可能になり、働き方の自由度が増しました。DX本丸と言うと私が申し上げてきたように、ビジネスをデジタル前提にするという話になるので、これを経産省に置き換えると、法規制や行政の執行をデジタルで考えることになるはずです。
例えば保安規制であれば、1年に1回、3日間立ち入り検査をするから作業を止めてください、といったやり方が従来の法規制の執行方法でした。しかし今では、センサーを付けてしまえば通年で監視できるため、本当に危ない時や企業の管理が適正でない時のみに検査すればいい。作業を止める必要もなくなり、お互いのコスト削減ができます。規制はしっかりとかかっている上での効率化というのが、デジタル技術をベースにしたルール執行のDX例になります。保安規制以外の法案に関してもDX化の推進と実証を始めている段階であり、それを増やしていくことが我々のDXの根幹になります。
DXは他人事ではありません。また企業が抱えるレガシーシステムを刷新して終わりでもありません。デジタル技術を活用し、ビジネスモデルを見直した継続的な提供価値のアップデートが重要になります。時には他企業との連携を強め、勝てるマーケットの見極めも求められるでしょう。DXの推進は、これまでにない重大な経営課題であり、日本企業がグローバルでも活躍するために必要な未来への投資とも言えるのです。