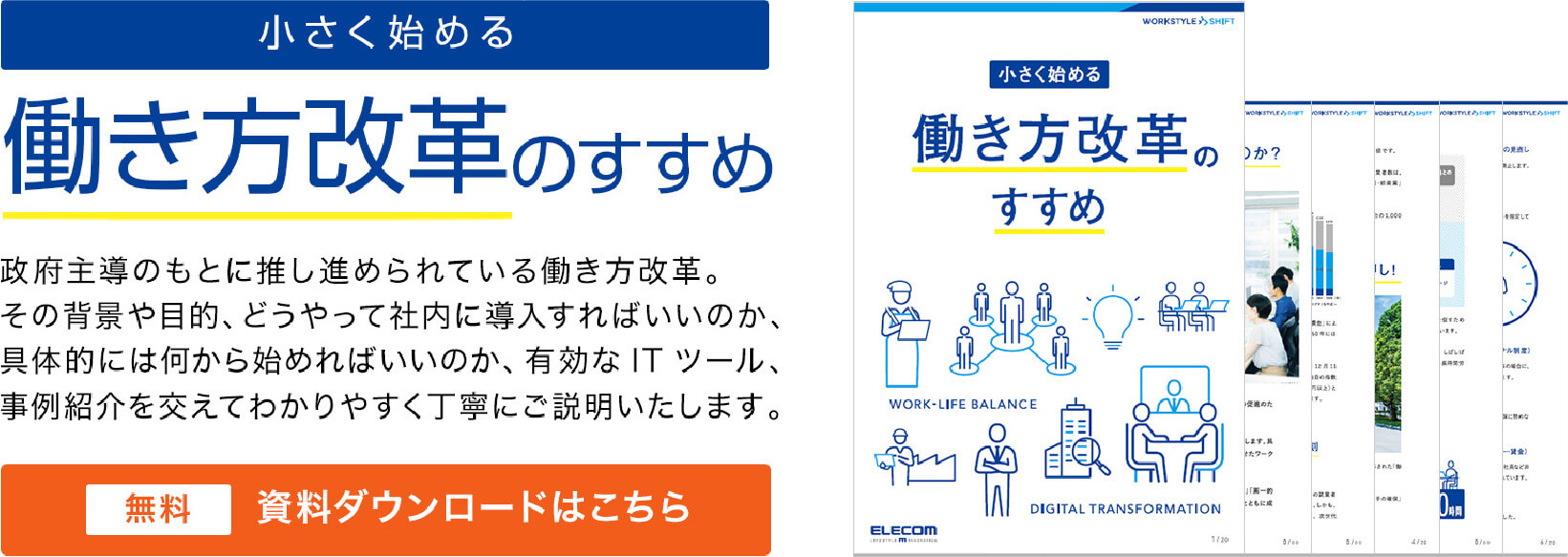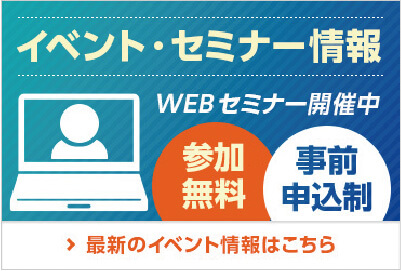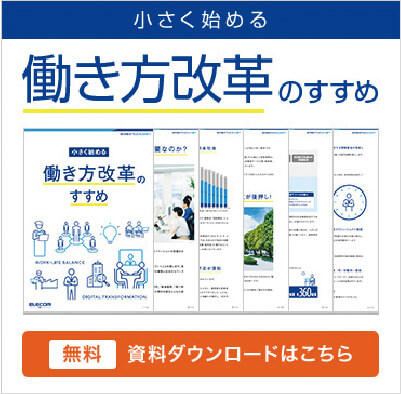店舗管理とは?店舗管理システムのメリットと導入のポイントとは?

「店舗ごとの売上分析をする時間がない」
「報告書の作成業務が煩雑だ」。
こうした悩みを抱える店舗運営者やオーナーは多いのではないでしょうか。売上や在庫、従業員の勤怠など店舗管理の業務は多岐にわたり、紙の伝票や表計算ソフトで数字を管理していると事務処理に多くの時間を割くことになります。
この記事では、店舗管理の内容や目的、課題を整理した上で、多店舗企業向けの店舗管理システムの内容と導入メリット、既存システムやタブレット端末との連携によるメリットなどをお伝えします。
店舗管理の目的と業務内容

店舗運営に関わる、売上、在庫、仕入、従業員といった「ヒト」「モノ」すべての資本の動きを把握することを、いわゆる「店舗管理」と言います。店舗管理は、経営の原動力である「ヒト」「モノ」を経営戦略に則って的確に管理することが目的となる非常に重要な業務です。
ひと口に店舗といっても「飲食業」「アパレル業」などさまざまな業種がありますが、「ヒト」と「モノ」が経営資源となるのは共通します。一見シンプルですが、その管理業務は多岐にわたり、店舗規模が大きくなるほど、オーナーや店長は業務が煩雑になります。店長であれば、上層部に報告を上げなければならず、負担が重くのしかかります。
ここでは、店舗管理の業務を「売上管理」「在庫管理」「仕入管理」「従業員管理」「顧客分析」の5つに大別して、内容を整理します。
●売上管理
毎日の売上高を把握するのが売上管理ですが、商品ごとの売上や時間帯などを把握していなければ、分析するに足るデータにはなりません。「手書きの伝票」で会計処理を行う飲食店だと細かい把握が煩雑になりますし、多店舗経営になるほど重労働になります。
◎小売・店舗は売上分析が重要。方法を学び、売上げアップを目指そう!
(上記記事、公開後内部リンク)
●在庫管理
売れ残った商品やこれから売る商品を「在庫」と言いますが、在庫の「増えた」「減った」を逐次把握するのが在庫管理です。在庫は増えれば増えるほど資金繰りが上手くいかなくなります。在庫が足りないと機会損失となるため、リアルタイムでの情報共有とニーズの把握、販売促進など多角的な視点が必要となります。
●仕入管理
店舗の販売商品を「どのくらい仕入れたか」「次は何をどのくらい仕入れるか」を把握するのが仕入管理です。適切な仕入を行うには、在庫や売上分析が適切にできている必要があります。多店舗経営になれば、店舗ごとに仕入の中身や量が変化するので、一元管理をすることが求められます。
●従業員のシフト、勤怠管理
従業員のシフト・勤怠管理も店舗管理における重要な役割です。特に従業員の勤怠が自己申告制だと、時間外労働・深夜労働の割増賃金の未払い、払い過ぎなどが起きる可能性があります。過不足なく必要な人員配置をする必要もあり、人件費の適正化を図る上でも正確な勤怠管理、シフトづくりは不可欠です。
●顧客分析
「誰が」「何を」「どのくらい買ったか」をデータ蓄積し、分析するのが顧客分析です。目的は購買予測です。例えば、年齢や性別、時間帯などでセグメントして分析することで、店舗の強みや改善点を抽出し、店舗経営に活かすことができます。
店舗管理には売上のデータ分析が必須!

店舗管理にはさまざまな業務がありますが、その中でも経営に直結する売上管理に焦点を当てて解説します。売上分析をする理由は、的確な「購買予測」を立てられるようにするためです。的確な購買予測を立てられれば、仕入戦略、在庫のさばき、従業員シフトを効率的に組み立てられるようになります。
営業上の課題を把握するには、いま置かれている状況を把握する必要があります。解決すべき課題を洗い出し、優先順位をつけて、売上分析の目的をより明確にします。また売上データを細分化すると、今まで見えなかったものに気付くことができます。
●商品別売上
商品別の売上高を確認します。売れ筋商品、または売れていない商品を視覚的に把握するのが目的です。
●月別売上
月別売上は、1~12月までの月ごとの売上高です。月別に売上を把握すれば、特定の商品が「夏場がピークで、冬場になると売上がピーク時より3割減る」など季節ごとのニーズを把握することができます。
●顧客別売上
顧客別売上とは「常連客」「安定顧客」「新規顧客」といった顧客の属性別に売上を把握する手法です。属性ごとの数値の高さや過去推移を把握するのが目的です。
●担当者別売上
担当者別に売上高、粗利などの数値を算出するのが目的です。
●部門別売上
部門別に売上高を算出します。スーパーマーケットなら「精肉部門」「鮮魚部門」など、どの部門が好調で不調かを把握するのが目的です。
●店舗形態別売上(ECや実店舗など)
店舗の形態別の売上も把握しておきましょう。衣料店なら「実店舗」「ネット通販」の2つの側面から見ます。過去推移と比較すれば、どの形態が好調で不調かを把握できるようになります。
これらの分析の他により高度な分析法として、顧客別の購買金額を分析する「デシル分析」と、顧客グループの性質を知るための「RFM分析」の2つがありますので、解説します。
デシル分析とは
デシル分析では、顧客を10等分にして分析をする手法です。例えば、100人の顧客を購入金額が多い順に10のグループに分け、特定期間の購入金額を算出します。10のグループの購入金額比率や累積購入金額比率、1人当たり客単価を割り出すことが可能となり、グループごとの比較ができるようになるため、顧客の属性化にも役立ちますし、どのグループにどのような施策を打つかを検討する材料となります。
RFM分析とは
RFM分析は、Recency(直近の購買日)、Frequency(購買頻度)、Monetary(購買金額)の指標で顧客をグループに分けて、常連や安定顧客、新規顧客などの特徴を把握するための分析です。かなり高度な分析法ではありますが、顧客データを取得・管理できていれば深い分析が可能となります。
店舗管理システム導入のメリットと活用法

売上分析に必要なデータを効率よく蓄積するには、店舗管理システムの導入がおすすめです。店舗管理システムを導入すると、店舗ごとの多角的な売上管理をスピーディかつ効率的に行うことができます。
POSデータが一元管理できるため、多店舗経営でも本部とリアルタイムに情報を共有できますし、これまでに説明してきた各種の分析も簡単に行うことが可能です。そのため、店舗責任者や本部の事務負担を軽減できますし、より迅速な経営判断も可能となります。
また、多くの店舗管理システムは誰でも使えるようにシンプルに設計されているため、操作が不慣れな人でも楽に使うことができ、汎用性が高いことが特徴です。会社ごとにカスタマイズできるサービスもあるため、業種に特化させることも可能です。
本部と現場店舗の連携が円滑になることで、次のサービスや施策を考える余裕が生まれます。単に数字を管理するだけでなく、本来責任者がやるべき「考えるべき業務」に集中する環境をつくることも大きなメリットと言えるでしょう。
導入のポイント
店舗管理システムを導入する上では、まずは、その店舗の業種・規模に合っているかどうかを基準に選びましょう。その上で、すでに使っている既存システムとの連携が可能かどうかも、大事な選定ポイントです。
例えば「飲食店向け店舗管理システム」の場合、発注や仕入の頻度が高いケースが多いため、その機能に特化したシステムを選ぶのもひとつの手です。その中でも、原価計算にかかわる仕入値・仕入先などの設定・変更が行いやすいシステムが適しています。
●タブレットやハンディPOSなどの活用
店舗そのものの規模が大きく、また多店舗展開しているような企業の場合は、タブレットやハンディPOS等の機器を利用すると、店舗管理がさらに便利になります。タブレット端末があれば、責任者は店舗内のどこにいてもデータの閲覧・共有が可能です。またPOSと連動したハンディターミナルを使えば、商品バーコードをスキャンして、棚卸業務や発注業務などを行えます。レジを置くスペースの確保が難しいシーンでの会計処理ができる点もメリットの1つです。
まとめ
店舗運営の原動力である「ヒト」「モノ」の動きや特徴を細かに把握する店舗管理。売上分析や勤怠管理などは表計算ソフトを使って管理できますが、店舗数が増えるほど事務作業は煩雑になり、店舗責任者やオーナーは、売上戦略に使える時間を捻出できなくなります。
そこで店舗管理システムを使って現場と本社でリアルタイムに情報共有できるようになれば、分析業務や企画戦略に時間をあてることができます。さらに多店舗経営の場合は、並行してタブレット端末やハンディPOSを使うと現場の動きがさらに効率的になります。一度、店舗管理業務の効率化を検討してみてはいかがでしょうか。