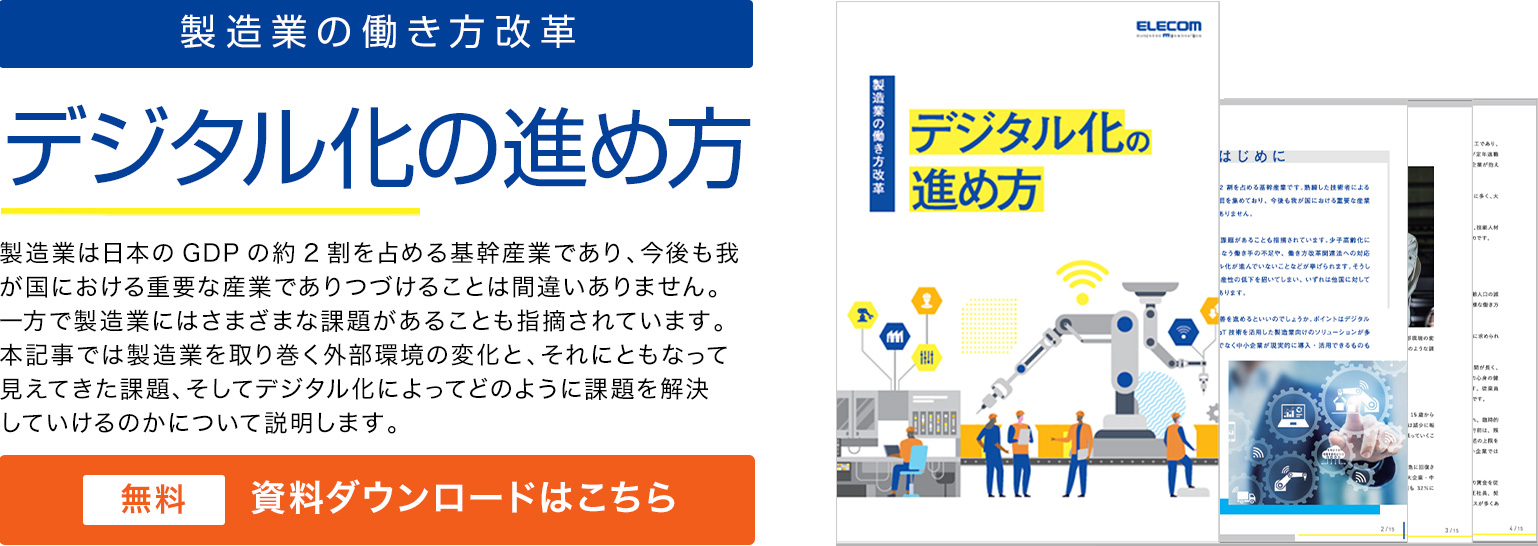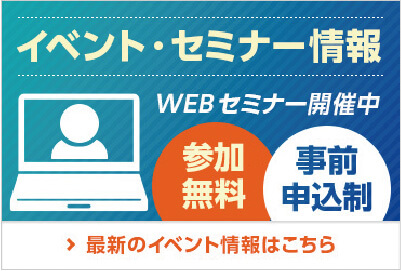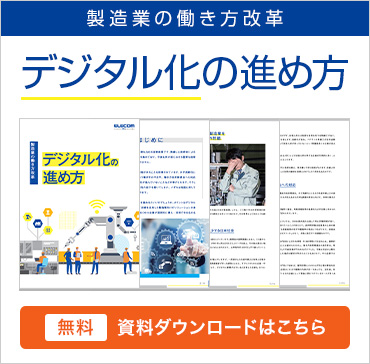ローカル5Gの必要性。仕組みや特徴、プライベート5Gとの違いは?
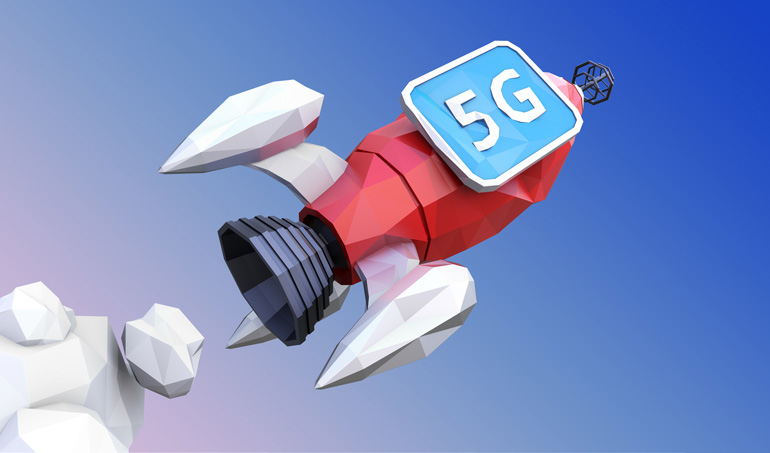
世界的なDX推進の流れにともない、ビジネスの場においても新たなネットワークである5Gの活用が議論されています。特に製造業などではローカル5Gが注目されており、近年では政府も推進しています。
ローカル5Gはそれぞれの特徴を把握した上で効果的に活用することが重要です。そこで今回は、ローカル5Gに注目して、詳しく解説していきます。
ローカル5Gとは?

ローカル5Gとは、キャリアに依存することなく企業や自治体が構築できる、5Gシステムによるネットワークのことです。
・超高速・大容量
・超低遅延
・多数同時接続
上記の3つが最大の特徴で、実際に企業や自治体がローカル5Gを構築する場合には、自社での免許取得や保守運用が求められます。
パブリック5Gとの違い
パブリック5Gとは、通信事業者(いわゆる携帯キャリア会社)が提供する5Gネットワークのことを指します。現行の4Gから5Gへの移行を目指し、現在、通信事業者各社がサービスエリアを拡大中です。
一方のローカル5Gは、企業や自治体が独自の5Gネットワークを構築・利用することから、サービスエリア外でも使用可能で、各通信事業者によるエリア拡大の進捗にとらわれる必要がありません。
プライベート5Gとの違い
プライベート5Gは、通信事業者の周波数を活用して個別に構築された、5Gネットワークのことです。企業や自治体など利用者の敷地内に、必要な帯域と容量の5Gネットワークを構築する点はローカル5Gと同様ですが、プライベート5Gは構築・運用を通信事業者に依頼するため、免許取得や保守運用などが求められず、手間がかからない特徴があります。
このような特徴から、プライベート5Gはローカル5Gとパブリック5Gの中間に位置づけられています。
ローカル5Gのメリット

ローカル5Gの導入は、先に紹介した3つの特徴「超高速・大容量」「超低遅延」「多数同時接続」に加えて、独自のネットワーク構築ゆえのメリットもあります。
代表的なローカル5Gのメリットは、次の3つです。
Wi-Fiより広範囲で使える
同時に複数接続できる無線通信と言えばWi-Fiが一般的ですが、接続できる台数や範囲が限られていることから、建物の面積が広大な工場などでは設置方法などに工夫が必要となります。一方のローカル5Gは、非常に広範囲で使用できる上、多数同時接続も可能です。
大規模な工場や建設現場、スタジアムなど広範囲でも問題なくカバーできるメリットは、業務の効率化に大きく貢献すると言えます。
外部環境に左右されない
通信事業者に依存しないことから、外部環境に左右されないこともメリットのひとつです。不特定多数のユーザーが利用する一般的なネットワークは、混雑で通信速度が遅くなったり、接続できなかったりすることがありますが、独自のネットワークを利用するローカル5Gであれば、外部の使用環境の影響を受けずに利用できます。
通信事業者に何らかの通信障害が発生した場合でも、ローカル5Gは影響を受ける心配がありません。
セキュリティに強い
前述のとおり広範囲で利用できるメリットがある一方で、展開するエリアを柔軟にカスタマイズできる点もローカル5Gの特徴です。独自のネットワークを研究所や工場など特定の範囲でのみ利用することができるため、情報漏えいのリスクを低減させます。
周波数によってはエリア外への電波の漏えいも少なく、外部を断絶した状態で利用することが可能なため、セキュリティに強い環境下でネットワークを運用できます。
ローカル5Gの注意点

利便性の高いローカル5Gですが、導入する場合にはメリットだけでなく、注意点も把握した上で検討することが重要です。事前に知っておくべきローカル5Gの注意点は、次の2つが挙げられます。
コストが高い
ローカル5Gに限らず、5Gによる通信は制御信号を扱うアンカーとして、既存の4Gのインフラを基盤とする無線アクセスネットワークを構成することで運用しています。この技術仕様をノンスタンドアロン(Non Stand Alone)と呼び、ローカル5Gを導入するためには、4Gと5Gの両方のネットワークを構築する必要があり、単純に基地局の数が増えコストがかかります。また基地局や交換機の多くは大手携帯会社向けです。処理性能や信頼性が高い専用ハードウエアの導入は相応の費用を必要とします。
現在、電波の出力や種類、設置場所に応じて以下の電波利用料が発生します。
・ローカル5G基地局:2,600円
・ローカル5G陸上移動局:370円
・自営等BWA基地局:19,000円
・自営等BWA陸上移動局:370円
自営等BWA:ローカル5G事業者等が、局所的な4Gの基地局、コアネットワークを自前で運用する仕組み
電波利用料は、いずれも基地局あたりの年額です。自営等BWAの構築作業なども含めると、ローカル5Gの導入と運用には手間とコストがかかることが分かります。
障害物に弱い
ローカル5Gで利用できる周波数は、28.2GHz~28.3GHz帯と4.6GHz~4.9GHz帯、28.3 GHz~29.1GHz帯です。28.2GHz~28.3GHz帯は直線的な電波を持つ周波数帯であるため障害物に弱い性質があります。そのため障害物の多い環境によっては通信できる距離が短くなるリスクがあります。
4.6GHz~4.9GHz帯も多く利用されますが、LTEや無線LANと同じ周波数であることから、同時接続数が多かったり容量の多い通信が行われたりした場合には、ローカル5Gのメリットである超高速・大容量の通信が困難となります。
環境や用途に合わせ選択する必要がある
上記のとおり、ローカル5Gは万能ではなく、環境によっては利便性が活かされないことがあります。快適に利用するためには環境と用途に合わせて、ローカル5Gを利用するかWi-Fiを利用するか、どちらが適しているかを慎重に検討することが重要です。
ローカル5Gの事例

ローカル5Gをビジネスに活用する企業は、国内外を問わず増加しています。最後に、すでにローカル5Gを導入している企業と、日本政府による取り組みの事例を紹介します。
アウディ:ローカル5Gの導入
ドイツの自動車メーカー「アウディ」は、以前から製造現場でWi-Fiを活用した産業ロボットの運用を行ってきました。2018年には、より高速な稼働とリアルタイムでのデータ収集を目的として、ローカル5Gの試験導入が行われています。
最初は一部のロボットのみに適用されていましたが、高い成果が現れていることから、全施設への導入を目指すことが発表されました。近年はドイツ国内の複数の工場で本格的なローカル5Gの導入が進められ、Wi-Fiから切り替えつつあります。
また、ドイツではアウディ以外の自動車メーカーをはじめ、化学工場やオイル、ガス、港湾設備関連企業など、さまざまな業種の企業がローカル5Gの導入に高い関心を示しています。すでに試験導入を始めている工場も少なくありません。
参考: IT Media『工場のネットワーク構築を「5G」でやる意味は?』
日本政府による『「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」に係る実証提案の公募』
前述したドイツの例だけでなく、米国や中国、韓国など多くの国がローカル5Gの導入に積極的です。世界各国でローカル5Gの導入・活用が進められている現状にともない、日本でも政府によるローカル5G活用を推進する活動が行われています。
「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」も、5G活用の推進活動のひとつで、具体的にはローカル5Gに関するより柔軟な制度の実現や、低廉かつ安心安全な利活用の実現を目的とした調査検討です。
開発実証の提案は公募され、政府より委託された企業と外部の有識者によって選定、実証企画が立てられます。令和3年度も開発実証の提案は公募されており、イベントや建設、農業、医療などさまざまな業界の企画が選定されました。
参考: 総務省『令和3年度「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」に係る実証提案の公募の結果』
まとめ~メリット・デメリットを把握した上で導入検討を進めよう~
ローカル5Gは、日本国内、海外を問わず多くの業種で導入が進められています。これまで述べたように、多種多様なメリットがあるため、積極的に導入していくと業務効率化が期待できます。
一方で、環境や用途によっては、ローカル5Gのメリットを引き出しにくいケースがある点に注意しましょう。メリットとデメリットの両方を把握した上で、適合した環境下でのローカル5G導入を目指すことが重要です。