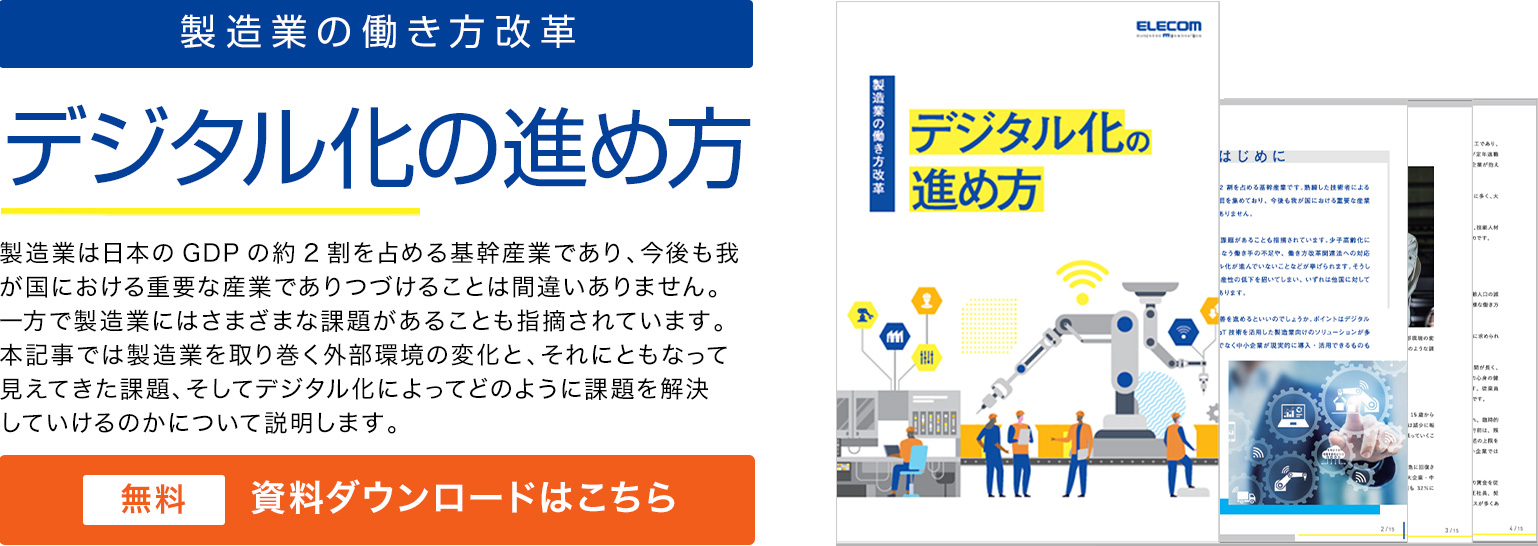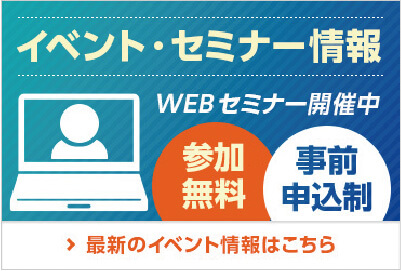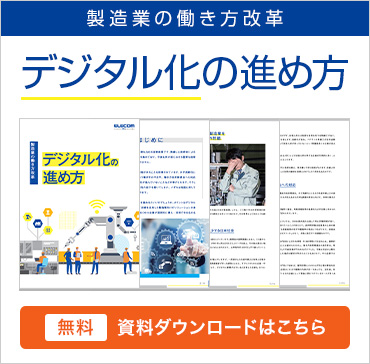「グリーン調達」とは? 企業が得られるメリットや取り組みの事例について

環境問題への取り組みは、消費者のみでなく企業にとって重要な課題です。特に、企業は環境に与える影響が消費者よりも大きいため、課題解決に向けたさまざまな取り組みの実施が求められます。この中で、注目される取り組みのひとつが「グリーン調達」です。このグリーン調達は、より良い環境をもたらすだけではなく、企業経営に対しても多くのメリットをもたらします。それでは、グリーン調達の定義やメリット、取り組み事例などを解説していきましょう。
グリーン調達とは
「グリーン調達」とは、企業が事業や業務を行うにあたって、環境に優しい原材料や部品、製品などを優先的に選び、購入する取り組みです。また、環境問題に関する取り組みに積極的なサプライヤーから、これらを調達する試みを指しています。
具体例としては、一般消費者に向けて加工食品を提供する企業が、環境や人に悪影響を及ぼさない原料や材料を調達するなどして、生産活動を行う試みが挙げられます。
また、グリーン調達とは似て非なる言葉に「グリーン購入」が挙げられます。グリーン調達と同義で使われるケースがほとんどですが、グリーン購入は一般消費者を含めた観点で、グリーン調達は生産者の観点で語られます。どちらの言葉も、“環境に配慮して購入先を選んだり、購入したりする意味”に違いはありません。
グリーン調達の目的や必要性
グリーン調達の目的のひとつに、環境対策に加え、バリューチェーンマネジメントの維持が挙げられます。バリューチェーンマネジメントとは、原料の調達から製造、物流、販売などまでの工程を分析・改善し、付加価値を最大化することです。グリーン調達はこのバリューチェーンマネジメントの中で特に、環境面での川上領域(製品を製造するために必要な材料調達の過程など)に焦点を当てて、付加価値を生み出します。
これまで環境に対する企業の取り組みは、環境に配慮した廃棄物処理や工場建設、生産方法などを中心に語られてきました。しかし、グリーン調達の概念は、自社の環境に対する取り組みではなく、取引を行う企業の環境活動などに目を向けるという意味で画期的だと考えられています。
グリーン調達が注目される背景のひとつには、CSR(企業の社会的責任)が挙げられます。昨今は、倫理的・社会的な観点から、事業活動を通じて社会貢献を行う企業が増加。CSRの一環として、グリーン調達に対する企業の関心が年々高まっていると見られます。
グリーン調達(グリーン購入)に関する法律
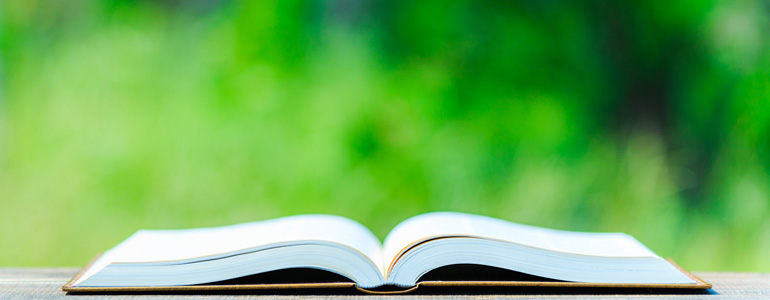
日本では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称:グリーン購入法)」でグリーン調達(グリーン購入)が規定されています。物品の品目や調達する際の基準などが定められており、企業はこれらに則して調達品を選びます。
しかし、法律で定められているものの、グリーン購入法に細かな罰則規定はありません。あくまでグリーン調達は、“企業が主体的に行うべき取り組み”として位置づけられているため、「自主調達基準」などと呼ばれるケースも見られます。
グリーン調達とISO規格
企業は、グリーン調達などに関連するISO規格の認証をISO(国際標準化機構)から受けることが可能です。ISO規格とは、あくまで取引を円滑に行うために定められた共通基準で、法的拘束力はありません。
ISO規格の認証を受けるにあたっては、製品の規格や生産フローに関するさまざまな項目の審査登録基準を満たす必要があります。認証を受けた企業は、共通基準に対して一定の要件を満たしているとして、取引などで優位になるケースがしばしば見られます。
例えば、ISO14001(環境マネジメントシステム)では、環境保全に関する計画や活動、改善などが制定されています。認証を取得した企業はコーポレートサイトに「ISO認証取得」と掲載する場合が多いので、コーポレートサイトは環境への取り組みを確認する上で一定の目安になるでしょう。
グリーン調達によるビジネスメリット

企業の中には、「グリーン調達はコストがかかるだけで、会社に多くの利益をもたらさない」といったイメージを持つ人がいるかもしれません。しかし、グリーン調達にはさまざまなビジネスメリットがあり、見方を変えると事業拡大などにもつながります。では、それぞれのビジネスメリットについて深く掘り下げていきましょう。
ステークホルダーからの信頼獲得
ステークホルダーからの信頼獲得は、グリーン調達の最も大きなビジネスメリットのひとつです。現在、環境問題への関心が社会で高まるにつれて、環境に対する厳しい視線が多くの企業に注がれています。こうした背景を踏まえると、グリーン調達の推進が、消費者や地域社会、納品先の企業、サプライヤーなどからの信頼獲得に寄与することは言うまでもありません。
さらに、ステークホルダーの企業に対する信頼が高まることで、企業のブランド力やイメージが向上。結果として売上増加につながる可能性があるかもしれません。
リスクの回避
グリーン調達の推進は、生産活動を脅かすさまざまなリスクの回避につながります。具体的なリスクとしては、国や行政の規制強化による事業機会の喪失が挙げられます。
例えば、企業が生産活動のコスト削減を狙って、環境に悪影響を及ぼす可能性がある物質を積極的に仕入れている場合、その物質の取り扱いが一度規制されると生産活動に大きな影響をもたらします。規制に対応することが難しい企業は、継続的な生産活動はおろか会社経営を存続できないリスクを抱える可能性もあるでしょう。
生産活動で扱われる原料や材料は、企業が予期せずとも、人や環境に甚大な影響を与えるケースが見られます。場合によっては、その企業が補償できない事態に発展するかもしれません。これらを踏まえるとグリーン調達は、単なる環境保護ではなく、企業のリスク回避にもつながる取り組みなのです。
取引の拡大
グリーン調達により、自社を取り巻くサプライチェーンの納品先などから信頼を獲得することで、企業は継続的な取引が可能になるでしょう。また、グリーン調達に関連するISO規格の認証取得で、企業は環境対策への取り組みを対外的にアピールすることができます。それにより新規取引先の獲得や、新しい事業の創出につながることが想定されます。さらに、納入先とサプライヤーとの間で環境対策に関する情報共有が進めば、品質改善などが進展するかもしれません。
グリーン調達に対する各企業の方針や事例

グリーン調達に対する方針や取り組み内容は、企業によってさまざまです。ここでは、日立グループ、株式会社トプコン、アマダグループの事例について、それぞれ紹介していきます。
日立グループの事例
日立グループでは、グリーン調達などに関する調査要領を3つのグループ(1. 環境保全活動の状況、2. 納入品に関する環境負荷低減の状況、3. 納入品の含有化学物質に関わる情報)に分け、上流サプライヤーを調査しています。
環境保全活動の状況調査については、ISO14001の認証取得、グリーン調達の実施などを項目に規定。また、含有化学物質に関する調査では、物質名や管理値などを示したリストを用いて、サプライヤーからの調達品を調べています。
トプコンの事例
光学機器などを手掛ける株式会社トプコンでは、調達品を品目特性で3つ(1. 商品に関する材料などの調達品、2. 生産活動に関する調達品、3. 文房具などの事務用品)に分類し、グリーン調達を進めています。
具体的には、生産活動に関する調達品を、設備・治工具類と塗料、メッキ液、シンナー、アルコールなどの副資材とし、「水質・大気・騒音・振動等の環境事前評価」や「新規原材料の化学物質の事前評価」制度によってグリーン調達を推進しています。
また、事務用品のグリーン調達については、環境に対する意識付けの観点から重要活動と捉え、再生材料使用品や分別回収可能品など環境に配慮した事務用品を積極的に選んでいます。
参考:トプコン「グリーン調達の取り組み」
アマダグループの事例
金属加工機械などを扱うアマダグループでは、調達品やサプライヤーに対する評価・選定基準を設け、グリーン調達に取り組んでいます。
サプライヤーに関しては、品質や価格、納期、サービス、環境保全活動への取り組み、含有化学物質の管理を評価対象とし、「『グリーン調達』取引先調査票」などに基づいて調達先を選別。一方、調達品については、不使用証明書などを用いて調達品の調査を実施し評価しています。
まとめ
グリーン調達に関する理解は深まりましたでしょうか。環境に関する企業の取り組みは、バリューチェーンマネジメントの促進や、「Sustainable Society(持続可能な社会)」を実現する上で非常に重要です。ぜひこれを機会にグリーン調達の実施を考えてみてください。