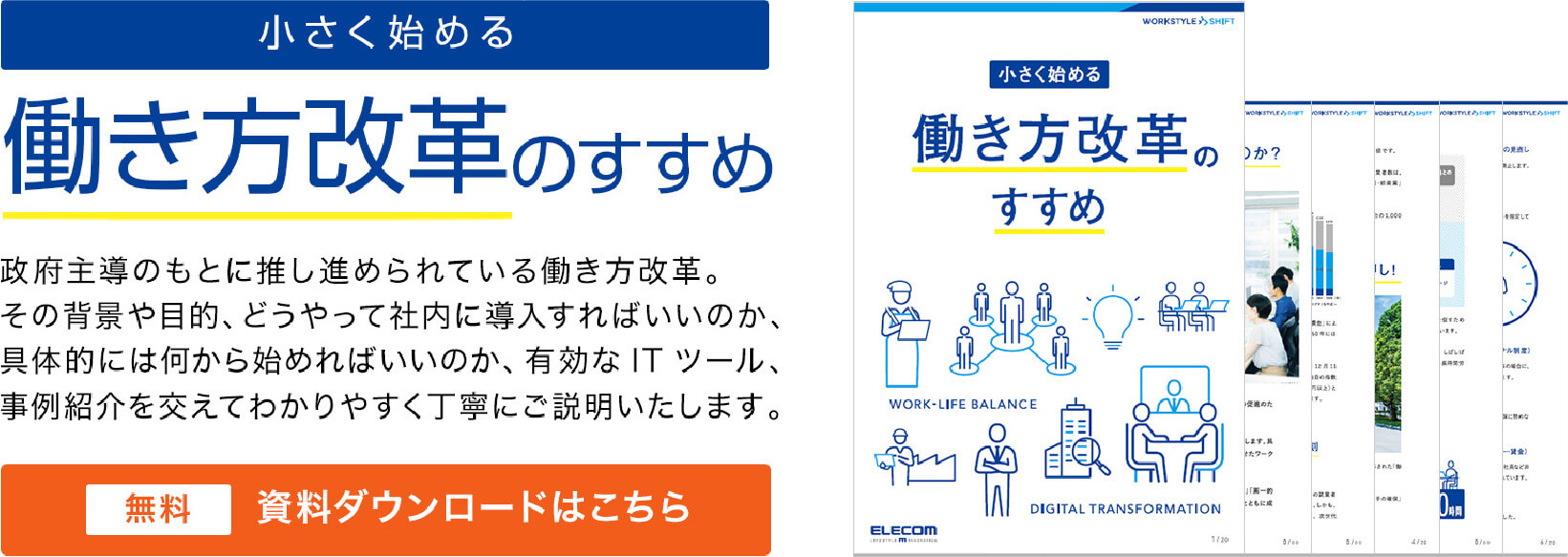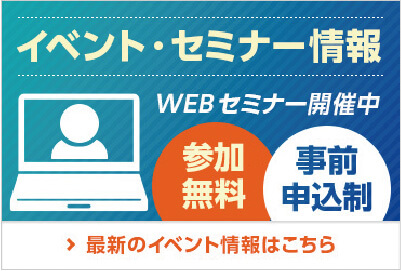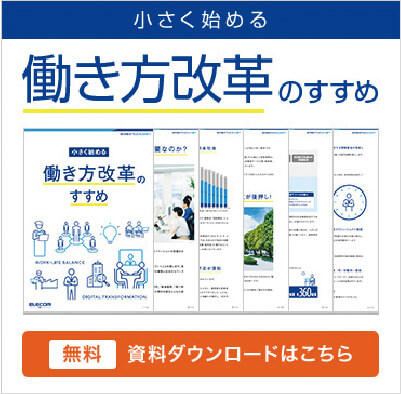時間外労働の罰則付き上限規制とは?企業が対応すべきポイントを含めて解説

2019年4月から働き方改革関連法が順次、適用されます。中でも注目を集めているのが労働基準法改正による「時間外労働の上限規制」です。これまでは特別条項付きの36協定を締結していれば、事実上上限がありませんでしたが、時間外と法定休日の労働時間を合わせ、最大で月100時間未満、2~6か月の平均で月80時間以内としなければ違法になり、罰則が科せられるようになります。企業によっては、業務効率化や就業規則の変更など早急に対策を講じなければならないでしょう。
今回は、「時間外労働の上限規制」の内容を解説し、長時間労働の原因と対策についても紹介します。
働き方改革関連法の中身をおさらい
働き方改革関連法は、改正労働基準法など8本の法律で構成されています。現在の日本は、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15~64歳)の減少や、育児・介護との両立など、労働環境の多様化に直面しています。これらの課題を解決するには、生産性の向上とともに、就業機会の拡大や意欲、能力を十分に発揮できる職場環境の整備が必要です。
このため、政府は2018年の通常国会を「働き方改革国会」と位置づけ、長時間労働の是正や同一労働同一賃金、多様な働き方の実現、脱時間給制度の導入などを目指す働き方改革法案を国会に提出しました。日本の労働慣行を一変させる内容だけに、激しい議論を呼びましたが、法案は2018年6月、与党などの賛成多数で成立しています。2019年4月から順次施行されますが、大企業・中小企業によって適用時期が異なるものもあります。下記をご確認ください。
働き方改革法の主な内容と適用時期
| 項目 | 適用時期 |
|---|---|
| 年次有給休暇の時季指定義務 | 【全企業】2019年4月〜 |
| 高度プロフェッショナル制度 | |
| 勤務間インターバル制度 | |
| 月60時間超の時間外労働の割増賃金 | 【中小企業】2023年4月〜 |
| 同一労働同一賃金 | 【大企業】2020年4月〜 【中小企業】2021年4月〜 |
●年次有給休暇の時季指定義務
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全従業員に対し、毎年5日、年次有給休暇を必ず取得させなければならなくなりました。従業員の申し出だけでなく、会社側が時季を指定して取得させることができます。
●高度プロフェッショナル制度の創設
脱時間給制度の高度プロフェッショナル制度は、年収1,075万円以上の一部専門職を労働時間規制から外すもので、働いた時間ではなく成果で評価するようになります。制度の導入には労使の合意と対象者本人の同意が必要です。
●勤務間インターバル制度
勤務間インターバル制度は、会社側に前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保するよう努力義務を課したものです。こちらも長時間労働の慢性化の防止と労働者の健康を確保する目的があります。例えば、所定労働時間が10時〜19時に設定されている企業において、繁忙期に業務が深夜の2時にまで及んだ場合、9時間の空きを作り、翌日の出勤は11時以降にするのが望ましいといった内容になります。
●月60時間超の時間外労働の割増賃金率の中小企業への適用
月60時間を超す時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金率での支払いが大企業に義務づけられる一方、中小企業は適用を猶予されてきました。しかし、2023年4月から猶予措置が廃止され、中小企業にも適用されます。
●同一労働同一賃金
同一労働同一賃金は、正規従業員とパート、派遣、有期雇用など非正規従業員との間で不合理な待遇差が禁止されます。
時間外労働の上限規制とは?

では、「時間外労働の上限規制」について詳しく説明しましょう。
労働時間には法定労働時間と所定労働時間があります。法定労働時間は労基法で定められたもので、「1日8時間、週40時間」と「少なくとも週1日の法定休日」の原則が設けられています。所定労働時間はこの原則に則り、各企業が「午前9時から午後5時まで、休憩1時間」などと設定した勤務時間を指します。
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合、労使協定で時間外労働をする業務の種類と時間外労働の上限を定め、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。この労使協定は労基法36条に基づくことから、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。36協定にも時間外労働の上限が設定されていますが、特別条項付きの締結をすることで、労使協定で定めた特別な事情に限り、上限を超えた時間外労働が例外として認められていました。
特別条項付き36協定を締結することで、際限なく時間外労働を行うことが可能となっていたため、現在問題となっている長時間労働の温床となっていました。しかし、今回の法改正により、下記のように定められることとなりました。
これまでも時間外労働の上限基準がまったくなかったわけではなく、厚生労働大臣告示で月45時間、年360時間の上限が設けられていました。しかし、違反しても罰則がないうえ、特別な事情がある場合の上限は設定されていませんでした。
月45時間、年360時間の上限が法律で明確に規定されました。36協定の特別条項で臨時的な特別の事情があるとして例外措置を認めた場合でも、以下のような制約が設けられます。
・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が「2か月平均」、「3か月平均」、「4か月平均」、「5か月平均」、「6か月平均」のいずれも月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
適用時期と罰則について
適用は大企業が2019年4月、中小企業が2020年4月からです。違反した企業には6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。労働基準法の運用に際し、労働基準監督署は「労働基準監督官行動規範」にて、中小企業の事情に配慮することが求められているので、余程悪質ではない限り1回目から罰則が科される可能性は低いでしょう。しかし、企業側からすると、罰則とならなくても企業イメージの低下や従業員のモチベーションの低下などデメリットしか存在しないため、長時間労働の是正にこれまで以上に臨まなければなりません。
<参照元:厚生労働省「労働基準監督官行動規範」>
長時間労働の原因と企業がとるべき対策とは

独立行政法人 労働政策研究・研修機構によると、2016年の日本の労働者1人当たりの平均年間総実労働時間は1,713時間です。ドイツの1,363時間、フランスの1,472時間、スウェーデンの1,621時間、英国の1,676時間に比べると、とても長いことが分かります。その原因はどこにあるのでしょうか。
<参照元:2018年「国際労働比較」>
長時間労働の原因
日本経済新聞社が経済産業省の委託を受け、2016年度に実施した働き方に関するアンケート調査では、経営者と役員、経営企画、事業企画、経営管理の部長職以上の82.0%が、自社で長時間労働が行われていると認識していました。全体・役職別・業種別に原因を見ていきましょう。
経済産業省の「働き方改革に関する企業の実態調査」
| 全体 | 管理職の意識やマネジメント不足 | 44.2% |
|---|---|---|
| 人手不足 | 41.7% | |
| 労働者の意識や取り組み不足 | 31.6% |
| 部長クラス | 長時間労働を是とする人事制度や職場の風土 | 40.0% |
|---|---|---|
| 社員の生産性やスキルの低さ | 35.7% |
| 製造業 | 経営層の意識 | 39.7% |
|---|---|---|
| 情報通信業 | 管理職の意識やマネジメント不足 | 56.3% |
労使双方に問題があることをうかがわせる結果が出ています。経営者や部長以上は50~60代が多く、日本企業が「エコノミックアニマル」などと海外で揶揄された昭和の時代にビジネスキャリアをスタートさせました。当時は24時間働くことが美徳のようにうたわれ、高い人事評価を得ていた時代です。時代が大きく変わりつつあるのに、意識が以前のままで企業風土を改善できないでいるのかもしれません。
人手不足で労働者1人ひとりが業務過多に陥っていることも大きな問題です。少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少は、今後も止まりそうにありません。政府は外国人労働者の導入に力を入れ始めましたが、よほど劇的な移民政策を取らない限り、現状打開が難しいと考えられています。
働き手が減る中で長時間労働を見直すとしても、労働時間の削減分だけ成果を減らすわけにはいきません。労働者1人ひとりがひたすら時間を費やして仕事をこなすのではなく、より短時間で大きな成果を上げられるよう働き方を変えることが求められます。
長時間労働への対策
では、長時間労働を是正するには、どのような対策が考えられるでしょうか。具体的な解決策を紹介します。
●経営層からのメッセージ
会社トップからのメッセージは強烈な意思表示となり、社内の意識浸透・共有にも非常に有効です。カゴメ株式会社では、社長自らメッセージを発信して働き方改革を主導しました。結果として、従業員の総労働時間を減らしながら、過去最高の売上・利益を実現。何のために改革をするのか? という目的を明確にすることで、初めて長時間労働は是正の一歩目を踏み出すことができます。
●人事評価制度の見直し
長時間労働を是正しようとしても、会社の人事評価制度が変わらなければ意味がありません。仕事への貢献度や目標の達成度などを加味した、従業員が納得する明確な基準が必要です。成果に対して評価されることで、長時間労働の是正にも直結します。また人事評価制度の変更に伴い、マネジメント層の意識の変化も期待できます。
●正確かつ客観的な勤怠管理
従業員の労働時間を正確に把握することも非常に重要です。働き方改革関連法でも「労働時間の適正管理」が求められていますが、実際にどの業務に携わっている従業員が、どのくらい時間がかかっているかなどを把握することで、課題の抽出に繋がります。労働時間を見える化することで、人員配置などに活かすことも可能になります。
●多様な働き方の制度化
業務効率をあげ、長時間労働を是正するためには、多様な働き方を推進する必要があります。多くの企業が導入しているのが、テレワーク(在宅勤務)やリモートワーク、フレックスタイムです。オフィス以外でも移動時間などを削減して効率よく勤務することで、業務効率化を実現できますし、ワーク・ライフ・バランスの確保にも結びつきます。
●ITツール、ICT環境の整備などデジタル機器の導入
働き方や制度の変更に伴い、オフィスのWi-Fi化やタブレットの導入など、必要に応じたツールを導入することで大きな業務効率化を実現できます。大企業ではRPAやAIの導入が進んでいますが、例えば各種書類をデータ化してペーパーレスを促進するなど、これまでの業務をデジタル化するだけでも大きな効果が望めます。
<参照元:経団連「働き方改革事例集」>
働き方改革にIT・デジタル化は不可欠

業務改善の点で大きな役割を果たしそうなのが、デジタル技術の導入です。政府は業務のデジタルトランスフォーメーションを企業に呼び掛けていますが、それは大企業に限った話ではなく、中小企業を含めたすべての企業に対してです。
中小企業庁が2017年にまとめた資料では、6割弱の中小企業がITツールやシステムを導入しているものの、その2/3が給与管理や経理業務などバックオフィス向けであり、収益に直結する業務では導入されていないことがわかりました。
中小企業がIT技術導入に及び腰になる主な原因は、ITに強い人材が不足していることや効果を予測できないこと、初期投資が必要なことです。しかし、現在は国や商工会議所など公的団体の支援制度や、初期投資が少ないクラウドサービスの充実もあり、導入が容易になってきています。
事実、中小企業庁が掲載している事例では、IT技術を導入した結果、大幅な売り上げ増を実現した神奈川県の温泉旅館や、労働時間短縮で効果を上げた大阪府の運送業者など多くの企業が紹介されています。
デジタル化はIoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、RPA(ロボットによる業務自動化)が次々に登場し、日進月歩の勢いで進化しています。これまでどうしても実現できなかったことが可能になり、仕事のスピードアップと負担の軽減を大きく助けてくれるようになりました。少人数で生産性を向上させながら、労働時間の短縮ができる時代になったのです。働き方改革のスタートまで、もはや待ったなしの状態です。自社の業務改善にどのようなツールが効果的なのか、早急に考える必要があるでしょう。
<参照元:中小企業庁「中小企業・小規模事業者のIT利用の状況及び課題について」>
まとめ
2019年4月から順次、適用が始まる働き方改革関連法。中でも時間外労働の上限規制は長時間労働という日本企業の悪弊を一掃し、働き方改革を実現するためのカギとなる施策と言えます。しかし、労働時間の短縮が生産性の低下に繋がったのでは意味がありません。社を挙げて時短に取り組む覚悟を示したうえで、ICT技術の導入で生産性の向上に結びつけなければならないのです。その先に見えるのは、意欲を持つ人が力を存分に発揮できる新時代の職場です。