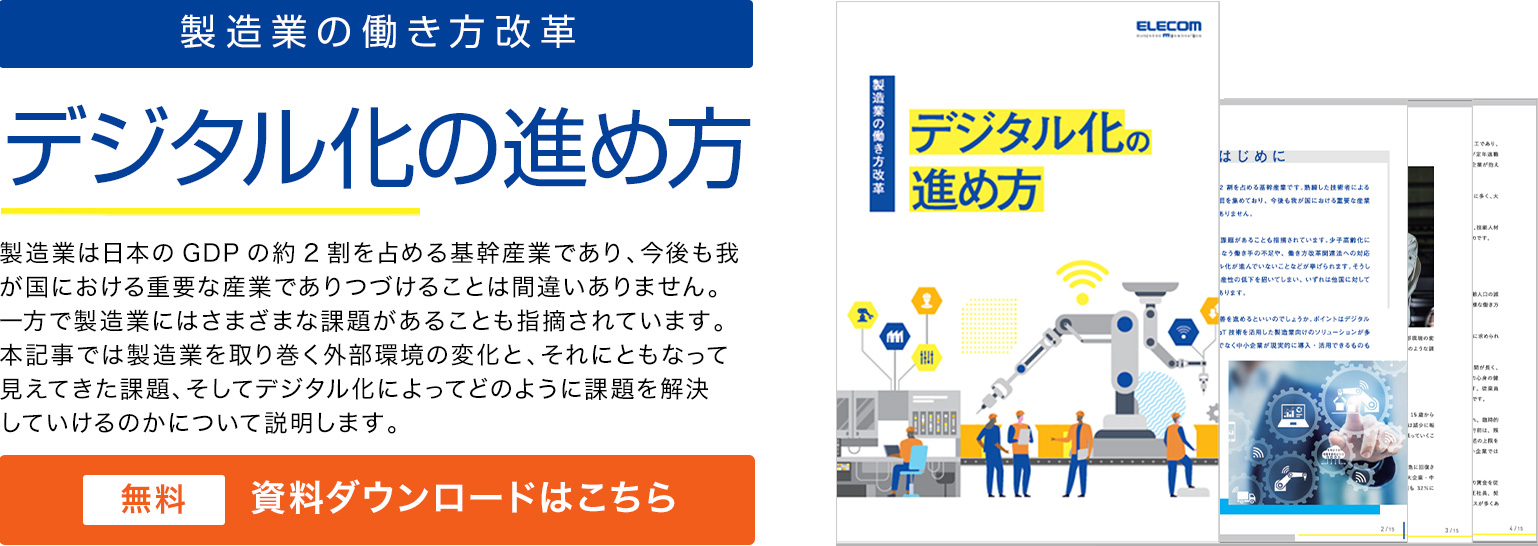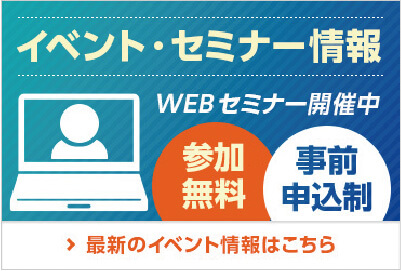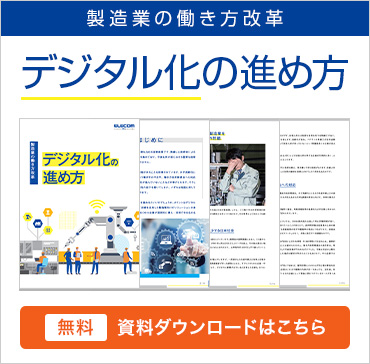予防保全とは? 予知保全との違いやメリット・デメリットを解説

製造業は日本経済の屋台骨として、長年我が国のGDP成長に大きく貢献してきました。その要となる工場を安定稼働させるために、企業はこれまで多くの資源を投入し、さまざまなノウハウを蓄積してきました。その最たるものの一つが保全行為です。
保全行為は大きく「予防保全」と「事後保全」に分けられますが、近年はIoT技術を活用した新たな保全行為である「予知保全」も注目されています。
それぞれどのような概念なのでしょうか。
本記事では、それぞれの保全行為の詳細とメリット・デメリットについて解説します。
予防保全とは?保全行為の種類

まずは従来型の保全行為である予防保全と事後保全について説明します。
予防保全
予防保全とは、工場内にある設備や機械の故障を防ぐために、メンテナンスを事前に行うことを指します。
具体的には、一定期間ごとに行う「時間基準保全」と、部品などの劣化状況に応じて不定期で行う「状態基準保全」があります。
特に前者の時間基準保全については、あらかじめ策定した「保全計画」に従い、点検や修理、部品交換などを定期的に行います。工場に行くと、日常点検や3ヵ月・半年・年間それぞれの点検やメンテナンスが設定されていることがありますが、これが時間基準保全になります。
このように、予防保全の中でも点検や部品交換のタイミングによって呼び方は異なります。
事後保全
事後保全とは、工場内にある設備や機械に何かしらの故障・不具合などのトラブルが発生してから対処する保全行為を指します。
トラブルの発生とセットで行われる保全行為なので、事前にスケジュールすることはなく、常に突発的な対応が迫られることになります。
予防保全がトラブルの未然防止を目的とするのに対して、事後保全はいかに可及的速やかにトラブルを解消するかに注力します。工場ラインが停止している場合は、時間が過ぎれば過ぎるほどに損害が大きくなるため、いかに迅速に復旧させるかがポイントになります。
この事後保全だけに頼った保全行為をしていると、工場の稼働が不安定になるリスクが高まり、結果として企業競争力の低下につながるため、注意が必要です。
予防保全より予知保全? IoTの活用

ここまでお伝えした予防保全と事後保全の他に、最近ではIoTを活用した「予知保全」への期待が高まっています。
予知保全とは、工場内にある設備や機械にIoTセンサーを取り付け、センサーを経由したデジタルデータを監視・分析する保全方法を指します。
取り付けられるIoTセンサーは24時間365日で稼働するケースが多く、工場の機械を常に定量的にモニタリング(監視)するため、あらかじめ設定した閾値(いきち)などを超えて故障や不具合の予兆を検知した際にアラートをあげます。そのアラートを確認した場合に、部品の交換などを行うことになります。
この予知保全が可能となったのは、前述したIoTセンサー技術の発達の他に、AI技術の発達も挙げられます。従来、センサーによって大量のデータが収集されたとしても、それらがどのような状態なのかを分析するのは人間でした。そのため、どうしても人力に頼った分析になり、量やタイミングの柔軟性に制限がありましたが、AI技術が発達したことでデータ分析機能が飛躍的に向上したため、無人でのモニタリングも可能になりました。
予防保全や事後保全との違い
予知保全は、保全行為のタイミングという観点では予防保全と同じです。
しかし、予防保全は定期的に決められたマニュアルに沿った保全行為なのに対し、予知保全はリアルタイムで機械の状態に応じて判断する保全行為となり、保全行為に対する費用対効果が高いと言えます。
それぞれ後述するメリット・デメリットを理解した上で、適切な保全行為を選択・実施しましょう。
予防保全と予知保全のメリット・デメリット
それでは、予防保全と予知保全のメリット・デメリットについて詳しくご紹介します。
予防保全のメリット・デメリット

予防保全には、以下のとおり3つのメリットと1つのデメリットが挙げられます。
メリット①:生産品質の担保
予防保全を行うと、定期的にメンテナンスを実施して部品などを交換するため、故障や経年劣化に伴う品質低下を回避できます。よって、常に高い状態の生産品質を担保できると言えます。
メリット②:ダウンタイムの回避
先述のとおり、事後保全はトラブルとセットの保全行為なので、実施する場合は工場ラインの停止が想定されます。
トラブルの内容によっては原因究明に時間がかかり、交換する部品の取り寄せに時間を要することから、ライン復旧までのダウンタイムが長期化するリスクがあります。
一方で予防保全の場合、定期的にメンテナンスをして機械の状態を維持するため、突発的なトラブルによるダウンタイムリスクを低減できます。
もちろん、あらかじめ策定された保全計画にない部分については定期メンテナンスが入らないため、すべてのトラブルリスクが拭えるわけではありません。よって、保全計画そのものについても定期的に見直しを行い、稼働の実態に沿った予防保全を行えるようPDCAを回すことが非常に大切です。
メリット③:スケジュール管理が明確なため従業員の働き方改善につながる
予防保全は計画的な保全行為が前提となるため、ライン稼働のスケジュール管理も明確に進められます。特に保全タイミングについて、事前にあらかじめ予定することができるので、休日や夜間の対応ではなく平日の営業時間中に設定できるでしょう。
つまり、メンテナンス担当の働き方にもポジティブに作用することが予測できます。
デメリット:事後保全や予知保全より作業工数が増える
一方で予防保全は、トラブルや予兆の有無とは関係なく定期的にメンテナンスを行うので、事後保全や予知保全よりどうしても作業工数が増えることになります。
また、特段問題がない部品についてもマニュアル通りに交換することになりますので、資源活用の観点でも課題があると言えます。
予知保全のメリット・デメリット

次に予知保全には、以下のとおり3つのメリットと1つのデメリットが挙げられます。
メリット①:生産ロスの削減
工場で発生するトラブルの中には、製品の不具合から事態が発覚するケースがあります。そのような製品は原因特定に利用された後は廃棄され生産ロスとなります。
一方予知保全の場合、あらかじめ定量的なデータをもってトラブルを回避するため、生産ロスの削減につながります。
メリット②:メンテナンスの最適化
前述のとおり、予防保全では交換の必要がない部品でも交換することになるため、メンテナンスの費用対効果は事後保全や予知保全と比べると相対的に低いと言えます。
一方で予知保全では定量的なデータから製品の不具合の予兆を分析して保全行為を行うことになるため、メンテナンスが工場オペレーションに最適化されます。部品コストはもちろん、保全行為に対応する担当者の人件費削減にもつながります。
メリット③:人員配置の最適化
上記に付随するメリットとして、予知保全は工場内の人員配置の最適化が可能です。
事後保全の場合、いつ機械が故障するか分からないため、常に対応スタッフを待機させる必要があり、また設備の監視役も必要でした。
一方で予知保全の場合は、IoTセンサーやAIが予兆を察知するところまで自動対応するため、監視役が常に張り付く必要はなくなります。また、予兆ベースで対応となるため、その分対応スタッフを常駐させる必要もなくなります。
デメリット:IoTデバイスなどの導入コスト
先述の通り予知保全は多くのメリットがある一方で、IoTデバイスなどの導入コストがかかるというデメリットがあります。最新のデバイス機器を導入する必要があるため、相応の費用がかかります。
ただし、ここまでお伝えした人件費や部品交換コストなどの削減、ダウンタイム発生による機会損失の予防に鑑みて、トータルでコスト面を判断する必要があるでしょう。
各メリット・デメリットを把握して保全行為への投資を検討しよう
トラブル発生を未然に防ぐことは不要なコストの削減にもつながるため、事業継続にとって重要な要素だと言えます。安定した事業継続のためにも事前の点検によってトラブルを防ぐ予防保全、そして故障や不具合発生後に対処する事後保全、さらにはより効率的に点検業務を行える予知保全の導入は欠かせません。
それぞれのメリット・デメリットを把握しながら、保全行為への投資を検討してみてはいかがでしょうか。