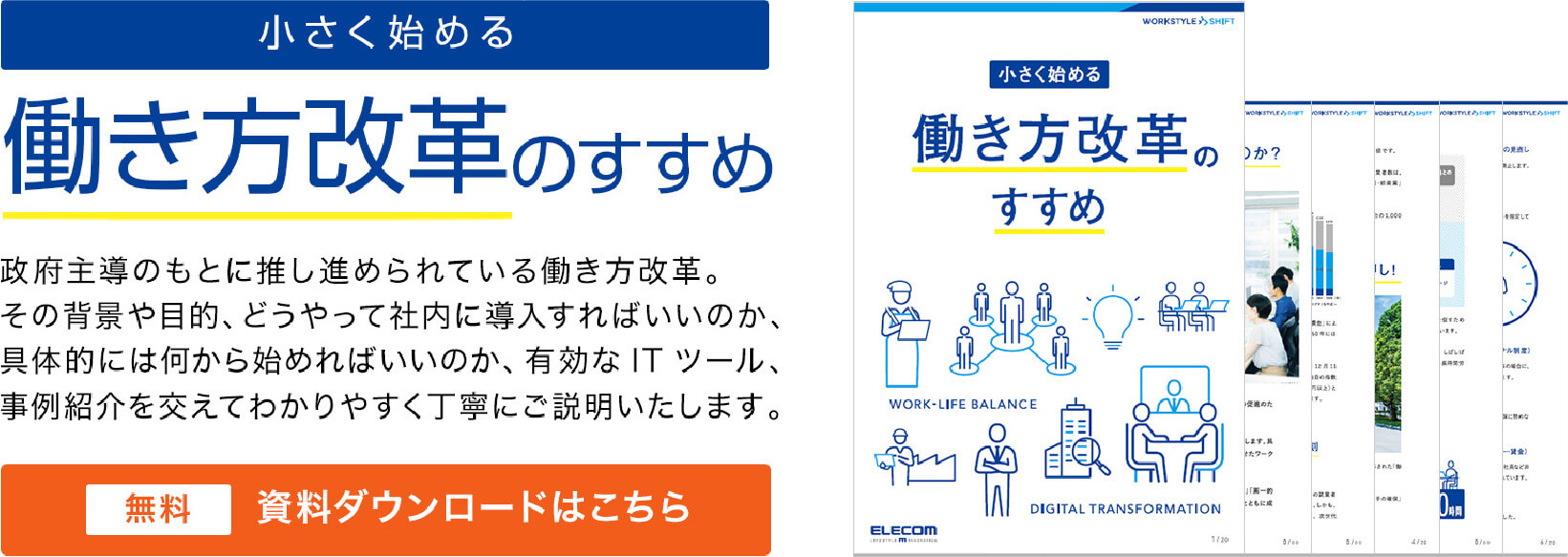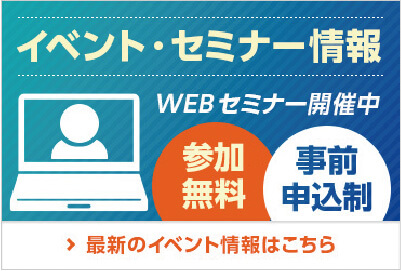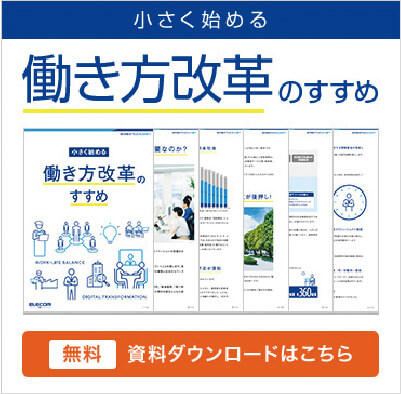経理の業務効率化を進めるIT施策とは?

現在、働き方改革に関する制度や生産性向上を目的としたIT、ICTツールが世の中に溢れています。業務効率化はどの企業にとっても至上命題ではありますが、「どこから」「なにから」着手をすればいいのか? という悩みもあるのではないでしょうか。
効果的なのは、ルーティンワークが多い業務から着手することです。ルーティンワークは定型的かつ反復的な作業となるため、ちょっとした工夫で大きな業務効率化を実現することができます。さまざまな業務の中でも、実は経理業務は他部署と比較するとルーティンワークが多いと言われています。
今回は、経理の業務効率化がなぜ必要なのか、という疑問に答えながら、Fin Tech(フィンテック)やRPAなどの最新サービスによる働き方改革の手法を紹介します。
経理部門の業務効率化が必要な理由

経理業務に業務効率化が必要な最大の理由は冒頭で触れた通り、「ルーティンワークが多いこと」です。では、経理部門にはルーティンワークはどの程度あるのでしょうか。経理業務を「日次」「月次」「年次」の3つに大別して説明します。
日次の業務
日々の業務を「日次の業務」と言います。日々取り交わされるお金の流れをすべて記録しなければいけません。現金や預金の出入金があれば、納品書や請求書、領収書がともなうため、そのすべてを整理、管理、保管し、集計する作業が生じます。以前は、手書きで伝票を書き、それを電卓で集計し、間違いがないかのチェックを繰り返していましたが、エクセルを使って行う現在でも同様で、手入力・チェックという業務がどうしても発生します。
月次の業務
月次では、1か月単位でお金の動きを管理します。月に1度発生する経理業務は、例えば請求・支払い業務、社員の給与計算、月次貸借対照表・損益計算書の作成などです。クライアントによって支払日や締め日が異なるため、把握した上で漏れなく対応しなくてはいけません。
年次の業務
年次では、年間を通じた取引を決算してまとめます。決算書の作成にとどまらず、税金の計算と支払い、年末調整、さらには保険料の計算と申告などを行います。経理業務の中で最も大事な業務と言われており、毎年同じ時期に発生します。
お金の動きを管理する経理部門では、些細なミスも許されません。売上金の入力を1円でも間違うと、正しい決算書が作成できなくなります。支払い金額が1円足りないと、取引として成立しなくなります。さらに請求や支払いも、締め切りが厳格に存在します。限られた時間の中で、正確かつスピーディな作業が、経理部門には求められます。
こうして「日次」「月次」「年次」業務を俯瞰すると、経理業務には「ルーティンワーク」や「手入力・手書き」が多いことがわかります。記帳や精算、請求・支払いといった作業は決まった手順で行える業務ですが、手入力のためミスも発生しやすくなります。これらの業務がテクノロジーにより自動化や効率化を図れるとしたら、その恩恵は大きいはずです。
経理業務の効率化を進めるFin Techとは

経理業務の自動化や効率化を進める上で鍵となるのがクラウド型サービス(SaaS)の活用です。その中でも経理や会計のサービスはFin Tech(フィンテック)と呼ばれています。Finance(ファイナンス=金融)とTechnology(テクノロジー=技術)を組み合わせた造語で、幅広い定義・サービスを含みます。例えば、仮想通貨や投資のロボアドバイザーからスマートフォンのアプリとクレジットカードや銀行口座を連携した決済サービスまで実にさまざまです。
そのようなFin Techの中でも法人向けサービスとして普及しているのが、下記のクラウド型サービスと言えます。
・会計業務の自動化、効率化
・請求書発行の自動化、効率化
・経費精算の自動化、効率化
・債権管理の自動化、効率化
では、上記4つを詳しく説明していきます。
クラウド型財務会計システム
会計業務の自動化、効率化のツールとして、認知度を上げているのが「クラウド会計サービス」です。
最大の特徴として、金融機関の取引明細やクレジットカードの購入履歴などの内容がクラウド会計の中に自動で反映され、一元管理が可能となることです。これまでエクセルに手入力してきた仕訳作業や請求書の作成も自動化、もしくは効率化します。手入力による手間やヒューマンエラーを劇的に減らすことが可能です。従業員の給与支払や経費精算も一体となったサービスでは、すべてがクラウド上で完結するため、経理担当者はもちろん従業員の経費精算の手間を省くことができ、給与明細もクラウド上で発行されるため、社内のペーパーレス化の一助ともなります。
請求書発行システム
請求書発行システムとは、帳簿作成・発行の自動化サービスです。帳簿の量が多い会社ほど効率化を期待できます。
使い方はシンプルで、豊富なテンプレートから使いたいものを選び、あらかじめ登録した取引先や品目を検索して入力するだけです。AI機能が搭載されたサービスでは、入力の自動補助機能で自動学習をするため、使うほどに作業が効率化します。
請求書発行の一括作成や取引先への送付サービス機能もメール送信機能だけではなく、システム上で郵送代行を依頼できるので、プリント、宛名書き、封入、投函などのフローを省けるようになります。
請求書発行システムを使えば、発行側は作業時間を大幅に短縮できます。入力ミス、郵送ミスのリスクを軽減できることもメリットです。サービスによっては、請求書の他、見積書、納品書、領収書といった書類の作成に対応しているなど機能は多様化しているため、導入の際には事前の確認が必要です。
経費精算システム
経費精算システムとは、交通費精算から立替経費精算、出張費精算などあらゆる精算業務を効率化するサービスです。交通費や出張費といった経費の精算業務は、これまで従業員がエクセルなどを使用して、日付や駅区間を入力している企業が多いのではないでしょうか。
ICカードと連携している経費精算システムでは、日付から路線、電車賃を毎回調べる手間を省ける上に、各従業員の定期券区間を自動的に控除してくれます。また経費申請から承認、処理までをシステム上で一括処理できるサービスが多く、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば外出先でも確認・操作が可能です。入力ミス防止のほか、社員の規定違反防止にも役立ちます。
債権管理システム
債権管理システムは、請求代金の回収効率を上げる目的のサービスです。企業が販売した商品やサービスは、多くが受け渡し時に販売代金が支払われない後払い決済です。こうした請求代金の回収を管理する債権管理は、購入日や入金日なども取引先によって異なるため煩雑で、経理にとってはミスが起きやすい業務です。こうした業務を一括で管理し、未回収や入金の延滞を自動通知してくれるのが債権管理システムの特徴です。回収効率が上がり、ミスの防止に役立ちます。
RPAによる自動化も徐々に普及

クラウド型サービスと並行して、いま急速に普及が進んでいるのが「RPA」(Robotic Process Automation=ロボティクス・プロセス・オートメーション)の活用です。2017年の総務省の調査によると国内で導入済みの企業が14.1%、導入中が6.3%、導入検討中が19.1%となっており、現在では5社に1社が導入していると考えられます。
近年では金融業界や大手企業が導入し、事務作業や経理作業を数千時間単位で削減していることで話題になっています。ここではRPAとクラウド型サービスとの違いや、メリット・デメリットを紹介します。
RPA・AIの特徴やクラウド型サービスとの違い
RPAでは、定型業務をソフトウェアロボットに学習させて自動化・効率化することができます。RPAにはクラス1から3までのレベルがあり、概要は以下の通りです。
| クラス | 主な業務範囲 | 具体的な作業範囲や利用技術 |
|---|---|---|
| クラス1 (RPA=Robotic Process Automation) |
定型業務の自動化 | 情報取得や入力作業、検証作業などの定型的な作業 |
| クラス2 (EPA=Enhanced Process Automation) |
一部非定型業務の自動化 | RPAとAIの技術を用いることにより非定型作業の自動化 自然言語解析、画像解析、音声解析、マシーンラーニングの技術の搭載 非構造化データの読み取りや、知識ベースの活用も可能 |
| クラス3 (CA=Cognitive Automation) |
高度な自律化 | プロセスの分析や改善、意思決定までを自ら自動化するとともに、意思決定 ディープラーニングや自然言語処理 |
<引用:総務省「RPA(働き方改革:業務の自動化による生産性向上)」>
一般的に普及しているのはクラス1のRPAで、定型業務であればロボットが自動で業務を代行してくれます。自動化・効率化という意味では、クラウド型サービスと似た印象を持ちますが、実は似て非なるものです。すでにシステムが出来上がっている各種クラウド型サービスと異なり、RPAは1から業務を学習させる必要があります。クラウド型サービスは「システムを使う」、RPAは「ロボットに作業を代行してもらう」といった違いがあります。そのためクラウド型サービスは人の手を介する必要がありますが、RPAは一度業務を始めると、基本的に24時間365日働くことが可能です。
RPAのメリット
ロボットがパソコンを使った定型、反復業務を代行してくれるため、業務担当者の作業効率が大幅に改善します。またロボットに作業を任せれば、入力ミスがなくなります。ロボットに業務を学習させるにあたり、プログラミングの知識が不要であることもメリットと言えます。また先述のとおり、24時間365日稼働ができるため、導入事例の多くの企業で省人化に成功しています。
RPAのデメリット
RPAのデメリットのひとつはシステム障害やバグによって業務が停止するリスクがあること。またネットワークにつながったRPAだとウイルスや不正アクセスによって情報が漏えいしてしまうなどが考えられます。また指示が間違っていてもロボットは忠実にその作業を遂行しますので、注意が必要です。RPAの運用・監視を専任とする担当者も必要になります。
RPA導入における業務効率化の恩恵は非常に大きいものですが、当然デメリットも存在します。自社の業務における課題点を的確に抽出して、適切なサービスを選ぶようにしましょう。
まとめ
お金が絡むすべての取引を記録・処理・管理・保管する経理業務には、精度とスピードが要求されます。決まった作業を繰り返すルーティンワークが多いため、システムやロボットを使った自動化・効率化を期待できる領域と言えます。
この記事で紹介した「クラウド会計サービス」「経費精算サービス」などのクラウド型サービスは、ノートパソコンやタブレット端末、スマートフォンにインターネット環境さえ整っていればすぐに利用できるものばかりです。外出先からシステムを閲覧・操作できるためテレワークなどの制度にも有効なことに加え、ペーパーレス化、情報漏えいの点でもメリットがあると言えます。
「人手不足」「長時間労働削減」といった課題を解消したい企業にとって、ルーティンワークの多い経理業務は、効率化のハードルが低く、取り組みやすい分野と言えます。働き方改革の第一歩を経理部門から始めてみてはいかがでしょうか。