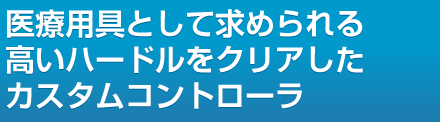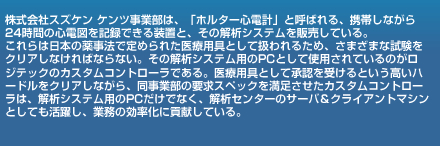株式会社スズケンは、1932年11月に「鈴木謙三商店」として名古屋の地で創業し、70年以上の歴史をもつ企業である。医療用医薬品の卸売事業を中核とし、ほかに医薬品や医療機器の開発製造、さらには全国に広がるネットワークから集まる医療現場の声を活かし、医療支援や健康支援などの医療関連サービス事業も展開している。2006年3月期には、グループ企業全体で、売上高1兆5千億円を超えるという国内でも有数の大企業である。
ロジテックのカスタムコントローラは、同社のケンツ事業部が扱う「コンパクトデジタルホルター心電計※」に記録された心電図データの解析システムに利用されている。
通常、心電図といえば、病院のベッドで横になった状態で検査することが思い浮かぶ。しかし、このような心電図検査は意外にも、わずか10数秒間の心臓の動きを記録しているだけなのである。この間に不整脈などの症状が現れる場合はよいが、1日のうちのわずかな時間にしか症状が現れない患者さんの場合、心電図検査では診断できないことがある。
一方「ホルター心電計」は、体に装着して携帯したまま自由に活動できるうえ、24時間連続で心電図を記録することができる。測定できる波形は一般の心電図の12チャンネルに対して、ホルター心電計では2ないし3チャンネルであるが、日中の活動時や夜間の安静時など日常生活の中で一時的にしか症状が現れない患者さんの検査には大きな威力を発揮する。また、以前はカセットテープを記録媒体として心音そのものを録音していたが、現在では電気的に測定した心臓の動きをデジタル記録してメモリに保存することで小型化を実現。同社のホルター心電計「Cardy(カルディ)シリーズ」はクレジットカードサイズで、薄さ15mm、電池を含めても重量がわずか72gというコンパクトサイズになっている。
ホルター心電計「Cardy(カルディ)シリーズ」に記録されたデータは、「デジタル記録ホルター心電図解析システム」のPCに取り込み、専門の臨床検査技師が解析ソフトを使って解析する。しかし、「デジタル記録ホルター心電図解析システム」は非常に高価なうえ、解析には医師または専門の臨床検査技師が必要なため、以前は規模の大きな病院でしか利用できなかった。そこで同社はホルター心電計を販売するとともに、社内にホルター心電図の「解析センター」を設置し、検査件数が少ない診療所や開業医、さらには大病院からも処理能力がオーバーした場合のデータ解析を受託するサービスを全国で展開している。
ロジテックのカスタムコントローラは、「デジタル記録ホルター心電図解析システム」に組み込まれているPCの最新モデルと、同社が名古屋/東京/札幌で展開する解析センターのサーバおよびクライアントマシンとして採用されている。
※1961年にホルター博士により開発されたために「ホルター心電計」と呼ばれている。 |