四方を広大な海に囲まれ、太平洋側には長さ800km、深さ8,000mにもおよぶ世界有数の海溝である「日本海溝」を有する海洋国家の日本。日本人にとって海はとても身近な存在である。その海を研究するのが「独立行政法人海洋研究開発機構」である。現在、地球環境、地球内部、海洋生物の研究と、これらの研究を進めるための探査機の技術開発、および地球環境と地球内部の研究に必要な「地球シミュレータ」のハードウェアおよびプログラムの開発・運用をおこなっており、こうした研究開発を通して人類の発展に貢献することを目指している。
同機構は、海洋の調査研究のために潜水船や探査機を複数保有している。6,500mまで潜航できる「しんかい6500」のような有人潜水調査船のほかに、7,000mまで潜航できる「かいこう7000」のような無人探査機がある。無人探査機は、母船とつながったケーブルから電源の供給と遠隔操作を受ける「ROV(Remotely Operated Vehicle)」と、探査機自身が電源を搭載し、自律航行が可能な「A U V(Autonomous Underwater Vehicle)」の2種類に分けられる。「かいこう7000」はROVに該当し、AUVには3,500mまで潜航できる深海巡航探査機「うらしま」のほか、試験運用中の海洋ロボット「MR-X1」などがある。
今回取材をした同機構 海洋工学センター 海洋技術研究開発プログラム 自律型無人探査機技術研究グループは、このAUVのより高度な運用に向けて、燃料電池などの電源技術、海中での位置の確認技術、自律性を高める運動制御技術など深海探査機の要素技術を研究している。そして、試験運用中の海洋ロボット「MR-X1」の船上装置の一部としてロジテックのカスタムコントローラが利用されている。 |
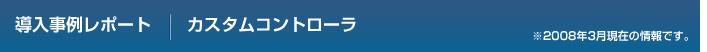
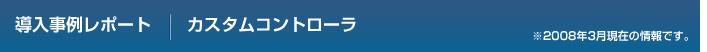

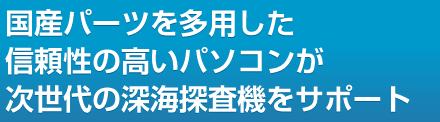
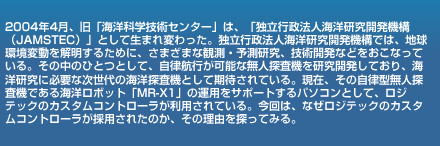
 今回、ロジテックのカスタムコントローラを採用した理由について、「19インチラックにマウントできること。そして国産メーカーのマザーボードと電源装置を使用していること。」と自律型無人探査機技術研究グループでMR-X1の開発を担当する吉田研究員は話す。
今回、ロジテックのカスタムコントローラを採用した理由について、「19インチラックにマウントできること。そして国産メーカーのマザーボードと電源装置を使用していること。」と自律型無人探査機技術研究グループでMR-X1の開発を担当する吉田研究員は話す。