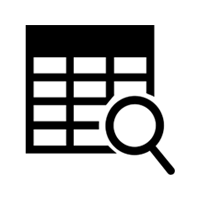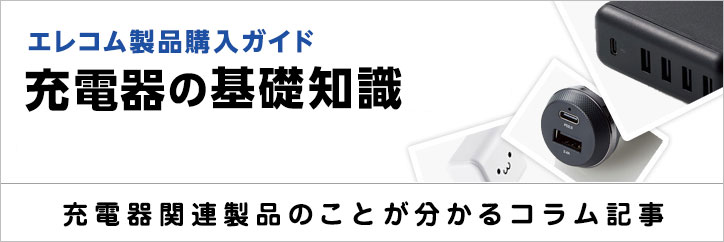スマートフォンやゲーム機器などバッテリーを搭載したデジタル製品を中心にUSBを使って充電をするシーンが、私たちの身の回りに広がってきました。
USBを使った充電は、これまではスマートフォンなどの小さなデバイスに限られていました。
しかし従来の充電規格に加え、「より高速で、より高出力」に対応した新しい充電規格ができ、それに対応したデバイスも増えてきています。
新しい充電規格によって、これまでUSBでは充電ができなかったノートパソコンやタブレットも充電ができるようになりました。

| 規格名 |   USB Power Delivery(PD) USB Power Delivery(PD) |
  Quick Charge(QC) Quick Charge(QC) |
従来規格 Type-C current @3.0A USB 3.0 USB 2.0 USB BC1.2など |
|---|---|---|---|
| 説明 | USB-IFが策定した、最大100wの充電が可能な、最新充電規格。USB PDと表記される。スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどが対応。 | クアルコム社が開発した最大18wの充電が可能な急速充電規格。Android搭載のスマホなどが対応。 | 最大15w |
| 充電器側 |   USB Type-Cに USB Type-Cに対応 |
  USB Type-Aに USB Type-Aに対応 |
  USB Type-A、 USB Type-A、Type-Cに対応 |
| デバイス側 |   USB Type-C USB Type-C、Lightningに対応 |
  USB Type-C、 USB Type-C、micro B に対応 |
  USB Type-C、 USB Type-C、micro B、 Lightningに対応 |
※USB Type-C™ are trademarks of USB Implementers Fourm.




バッテリーを搭載した機器への充電は、イメージとして注射器でコップに水を貯めることに似ています。

バッテリーを搭載した機器への充電は、イメージとして注射器でコップに水を貯めることに似ています。
- ・注射器が充電器
- ・水が電気
- ・コップがバッテリーを搭載した機器です。
コップにどれだけ早く水を貯めることができるか、つまり電力を供給できるのかがポイントとなります。



-



注射器を押す力= 電気を流そうとする力です。
単位はボルト(V)で表します。 -



注射器から押し出された水の流れ= 流れる電気の量です。
単位はアンペア(A)で表します。 -



コップに貯まった水の量= バッテリーに供給される電気の量です。
単位はワット(W)で表します。

充電性能は、ワット(W)という単位で表します。
ワット(W)は、・注射器の針の太さ=電流(A)と・注射器を押し出す力=電圧(V)のかけ算で求めることができます。
充電性能(W) = 電流(A) ×電圧(V)



-
従来規格の充電方法
従来規格では、早くコップに水を貯めるために、注射器の針を太くしていました。つまり、出口を大きくすることで、流れる電気の量=電流を増やし、電気が早く貯まるようにしていたのです。

1Aの充電器と、2.4Aの充電器では2.4倍の電流を流すことができ、その分だけ充電スピードも早くなります。
-
新しい規格の充電方法
新しい高速充電規格では、さらに早くコップに水を貯めるために、注射器の針を太くすると同時に、水を押し出す力も強くできるようになりました。

つまり、出口を(電流)大きくし、より強い力(電圧)で押し出すことで、充電速度を早めるのです。

近年対応するデバイスが増えているUSBの充電規格が、USB PowerDelivery(パワーデリバリー、以下「USB PD」)です。USB PDは、「USB Type-CのコネクタまたはLightningコネクタがある、USB PDに対応した機器」で利用することができます。
iPhone XS、iPhone XR、XPERIA XZ3、Galaxy Note9、Pixel3などスマートフォンの最新モデルの多くがUSB PDに対応しています。
USB PDは最大100Wという従来規格よりも高い出力に対応しており、スマートフォンだけではなくノートパソコンや、タブレットなどにも採用され始めています。



USB PDは最大100Wという高い出力なので、iPhoneやiPadに付属している5W(5V/1A)出力の充電機器と比べると、20倍ものパワーを持っていることになります。
給電する出力が大きいということは、その分、充電の速度が早いということ。
例えば、ELECOMのPD18Wは、30分時点での充電量が付属品の約2.3倍!
スタートアップで差がつくのが特徴です。USB PDはとてもパワフルな規格なのです。




| 端末 | AC充電器 | 30分時点での 充電量 |
充電完了時間 |
|---|---|---|---|
| Xs | 本体の 付属品(1A) |
22% | 3:00 |
| ELECOMの PD18W製品 |
52% | 2:05 | |
| XS MAX | 本体の 付属品(1A) |
17% | 3:30 |
| ELECOMの PD18W製品 |
54% | 1:50 | |
| XR | 本体の 付属品(1A) |
19% | 3:10 |
| ELECOMの PD18W製品 |
54% | 1:45 |
※2019年8月 当社測定による

| 端末 | AC充電器 | 30分時点での 充電量 |
充電完了時間 |
|---|---|---|---|
| ipad air (2019) |
本体の 付属品(1A) |
22% | 3:00 |
| ELECOMの PD30W製品 |
52% | 2:05 | |
| ipad pro (12.9インチ) |
本体の 付属品(1A) |
17% | 3:30 |
| ELECOMの PD45W製品 |
54% | 1:50 |
※2019年8月 当社測定による

USB PDでは充電器側とデバイスが通信を行い、充電器側の最大出力までの範囲で、デバイスに最適な電圧、電流、出力を自動選択します。
各デバイスに最適な出力以上の「最大出力」を持った充電器が必要となります。
各デバイス W数の目安
-
約18W


iPhoneなどのスマートフォン
-
約30W


iPad Proなどのタブレット、MacBookやLet’s Noteなど、モバイルノートPC
-
約45W


MacBook Pro 13inchや、ThinkPadなど、一般的なノートPC
-
約65~100W


MacBook Pro 15inchなど、ハイスペックノートPC
複数のデバイスを同時に充電する場合、全デバイスの合計W数が必要になります。
USB Type-Cケーブル1本で電力供給はもちろん、データ通信も同時に行うことが可能です。ノートパソコンと外部ディスプレイをUSB Type-Cケーブルで接続すると、映像を映しつつ、ノートパソコンを充電することができるため、配線をシンプルにすることができます。




Quick Chargeは、Android搭載のスマートフォンを中心に採用されている、米国のQualcom(クアルコム)社が開発・提供している高速充電規格です。「USB Type-Cもしくは、Micro Bメスコネクタがあり、Quick Chargeに対応した機器」で利用することができます。

Quick Chargeにはいくつかのバージョンがあり、最も広く使われているQuickCharge3.0では、QuickCharge2.0と比較して、最大27%の充電速度を実現しています。QuickCharge3.0は2.0との下位互換があるため、QuickCharge3.0対応の製品は、2.0対応の製品にも使うことができます。

QuickCharge3.0は、「Intelligent Negotiation for Optimum Voltage (INOV)」と呼ばれる技術が採用されています。これは最も効率よく急速充電を行うために、デバイスに応じて電圧と電流の両方を最適なレベルに自動調整するものです。

QuickCharge3.0対応の充電器選び

Quick Chargeに対応した製品には、
「Quick Charge認証ロゴ」が記載されています。
また、最大出力の表示にも着目しましょう。電圧(V)、電流(A)の数値が大きいほど、より高速で充電が可能です。



USBはパソコンと周辺機器を接続する規格として、1990年代から採用をされています。当初は、マウスやキーボードなどの周辺機器とパソコンとの間でデータの転送をすることが主な役割でした。USBの仕様として、同じコネクタで給電も可能だったため、徐々に充電の役割も担うようになります。2000年にUSB2.0が発表され、2008年にはUSB3.0が発表されます。USBを使った充電の機会が増えUSB3.0では、最大のデータ転送量が増えるとともに、給電能力も500mA(ミリアンペア)から、900mAに引き上げられました。さらに給電能力を高めた、USBBC1.2は、最大1500mAまで給電できるようになっています。USB3.1から追加されたTypeC端子ではUSBTypeCcurrent@3.0A(3000mA)が追加されています。