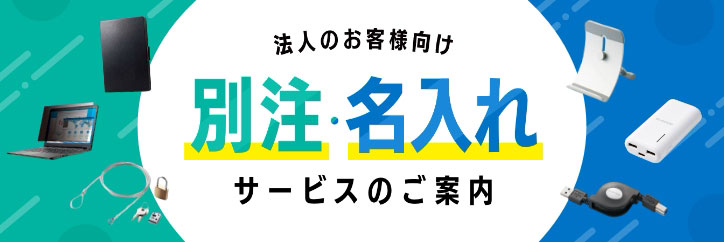大阪府立支援学校で、
教職員のコミュニケーション向上に
エレコムのデジタルサイネージが貢献


- 導入レポート
大阪府立 思斉支援学校 様 - 大阪府立思斉支援学校様は、昭和15年設立の日本で最も歴史ある知的障がい支援学校(設立当時は大阪市立)である。
同校では、教職員の数も多くコミュニケーションをいかに向上させるかが課題となっていた。
この度、同校ではその解決策の一環としてエレコムのデジタルサイネージ『掲示板NEXT』を導入。
その経緯や運用方法などについてうかがった。
日本で最初に設立された知的障がいのある児童生徒を対象とした支援学校
児童や生徒が「明日も行きたいと思う学校」をめざし、地域で豊かに生きていく力の育成を目標にしている思斉支援学校様。同校では、豊かに生きていく力として、「豊かなこころ」「楽しむ力」「体力」「コミュニケーション力」の4つの力の育成を大切にしておられる。同校には、小学部・中学部・高校部があり、約350名の児童生徒が、通学バスや公共交通機関、保護者の送迎などで通学している。
教職員間のコミュニケーションを円滑化するためデジタルサイネージを導入

校長の井上氏によると、同校のみならず全国的な傾向として知的障がい支援学校に通う児童生徒数は増加しているのだそうだ。
「少子化で子どもの数自体は減少していますが、知的障がい支援学校に通う子どもの数は増えているんです。そんな中、いかに支援の必要な子どもたちに行き届く教育をということで教職員一同がんばっている状況です(井上校長)」
支援学校に通う児童生徒の増加に対応するため、教職員の数も増加。さらに、消毒作業などコロナ対策を行うスタッフの雇用も重なり、臨時職員も含めると現在は約180名弱の教職員が在籍しているという。
「教職員には働く時間帯が異なる方もいます。また、働き方改革を進めるなか、全員が一定の時間に職員室に集まるというのも改革の流れに反するものです。さらに、コロナ禍の影響もあり大人数が密集することは避けたいという事情もありました。そこで、デジタルサイネージで情報伝達をサポートするのはどうだろうという話になったのです(井上校長)」
学校にデジタルサイネージを導入するにあたっては、井上校長の過去の経験も大きかったという。
「私が以前、教育委員会に勤務していた時、聴覚支援学校の担当をしたことがありました。そこでは、学校放送が聞こえない生徒もたくさんいるので、『見える学校放送』としてたくさんのデジタルサイネージを学校中に導入しました。その方法を取り入れてみようと思ったのです(井上校長)」
セキュリティ上の制約下での最善手として『掲示板NEXT』を採用

天井面に取り付けられたデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス)。
デジタルサイネージの導入を念頭に、いくつかのメーカーのサービスを比較したのは教頭の紙野氏だ。しかし、府立学校である同校には、非常に厳しいセキュリティ上のルールがあるのだという。
「教員のPCは、基本的に外部ネットワークにつながっていません。また、クラウドサービスなどを利用して月々のランニングコストがかかることは、導入のハードルをさらに上げることになります。いろんな制約のなかで、いかにやりたいことに近いことができるかを考えていかなければならないということで、リコーさんにアドバイスを求めました(紙野教頭)」
同校から相談を受けたリコーの担当者は、数あるサービスの中から、クラウドを利用せず月々のランニングコストもかからないエレコムの『掲示板NEXT』を推奨したという。
「簡単なオペレーションで、職員間の連絡に使いたい。ランニングコストもかけたくないということで実績のあったエレコムさんを紹介しました」と担当者。その後、紙野教頭らは同社の展示会を訪れ、実機のデモを見て導入を決められた。
2つの職員室に4台の液晶モニターを設置

職員室に入るとすぐに目に入る場所に取り付けられたデジタルサイネージの液晶モニター。
思斉支援学校様には、大小2つの職員室があり、大きい職員室に3台、小さい職員室に1台の65インチ液晶パネルが導入されている。
「翌日の予定や来校者、注意事項、子どもの欠席状況などを夕方5時ぐらいに先生方がワードで入力し、それを私がPDFに変換し、翌朝8時から9時半までそれが流れます」そこへ例えば『何号車のバスが遅れる』といった情報が入れば、私がテキスト入力して掲示します(紙野教頭)」
通常は、ワードやパワーポイントなどのオフィス文書やPDFをそのままコンテンツ化して運用。一方、急な伝達事項が発生した時には「メッセージボード」機能も利用されている。これは、チャットツールのような感覚で複数のメッセージのやりとりを掲示できる機能で、通学バスの遅延や児童生徒に関する緊急の連絡などに役立てられている。
「また、放課後、帰りの通学バスが出たあと3時15分から4時までが教職員の休憩時間になります。だいたい職員室でコーヒーを飲んだり、その日の振り返りなどを行ったりするのですが、こういった時にもサイネージに情報を流します。例えば、教員研修の資料や、支援学校に関する情報やデータなどをスライドショーにして流しています。忙しくて研修に行けない先生への情報共有ですね(紙野教頭)」

チャット感覚で緊急のやりとりを掲示し、教職員間で共有できる「メッセージボード」機能。

モニターには、日々の連絡事項のほか、研修資料や支援学校を取り巻く最新情報なども掲示される。
パソコンを立ち上げることなく必要な情報を共有
取材時点で、約1か月半にわたり運用されてきた『掲示板NEXT』。その感想はどんなものだろうか。
「私たち管理職から、教職員の皆さんに必要事項を伝達するチャネルはいろいろあります。デジタルサイネージの導入で、その大きなチャネルの一つが加わったという印象ですね」と紙野教頭。
「朝、児童生徒の出迎えで忙しい中、パソコンを立ち上げなくても伝達事項が伝わるのはとても便利で助かるという声を聞いています」と語るのは橋本首席だ。
日々、連絡事項や伝達事項の発信、緊急時の連絡などに『掲示板NEXT』を活用されている思斉支援学校様。今後は、さらに有効に利用するため、教職員からアイデアを募っているという。
障がいのある子どもに寄り添ったICT機器の開発をお願いしたい
タブレット端末を全児童生徒に配布するなど、教育のICT化を進めている同校では、いかにその効果を高めていけるかが今後の課題だという。
「通常の学校のように、教室の前方にモニターや拡大表示装置をセッティングするといった運用は、支援学校の授業の実態としては難しいのです。
タブレット端末を全児童生徒に配布するなど、教育のICT化を進めている同校では、いかにその効果を高めていけるかが今後の課題だという。
「通常の学校のように、教室の前方にモニターや拡大表示装置をセッティングするといった運用は、支援学校の授業の実態としては難しいのです。もっとフレキシブルに、モニターや関連機器が移動できると便利なのにと思います。メーカーさんには、ICTの側から支援学校の児童生徒に寄り添うような機器やサービスの開発をぜひお願いしたいですね(紙野教頭)」
取材にご対応いただいた方

- 大阪府立 思斉支援学校
校長
井上 昌二氏

- 教頭
紙野 泰彦氏

- 首席
橋本 修司氏

大阪府立思斉支援学校
小学部・中学部・高等部を持つ大阪市旭区の支援学校。令和2年に創立80周年を迎えた。校名の由来は『論語』の「子曰く賢を見ては斉しからんことを思い 不賢を見ては内に自ら省みるなり」より。
大阪府立思斉支援学校ホームページ
https://www2.osaka-c.ed.jp/shisei-s/

ご採用機器

デジタルサイネージ用BOX PC for Android™ LB-HMB545-KNMB
- 4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス)。
ご採用ソリューション
-
月額コストゼロ
クラウドサーバ不要だから
月額コストがかかりません。
-
簡単操作
コンテンツ作成、
スケジュール配信も簡単。
-
クイックスタート
複雑な設定なしで利用開始できます。

掲示板NEXTは、クラウドサーバ不要のオンプレミス型の高機能サイネージ。さまざまな素材を自由に配置し、コンテンツを作成することができます。
■配信ソフトウェア特長
-
さまざまな素材を自由に配置
静止画、動画、テロップ、WEBの4種類のデータを素材として取り込み、好きな場所にドラッグ&ドロップで配置するだけでコンテンツをつくることができます。

-
インタラクティブサイネージも手軽に作成
配置した素材に対してリンク先のコンテンツを設定していくだけで、簡単にタッチで画面が切り替わるインタラクティブなサイネージコンテンツが完成します。

-
柔軟なスケジュール設定
15分間隔で細かく時間割を設定したり、曜日ごと、日付ごとに異なるコンテンツを放映したり、柔軟なスケジュール設定機能でお客様のご要望を実現します。

-
緊急時など、1クリックで
放映コンテンツを差替可能1クリックでコンテンツを瞬時に切り替えることができます※。緊急時など急ぎのときに有効な機能です。
※切り替えるコンテンツは事前に設定しておく必要があります。