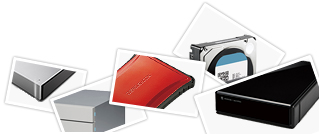
NASにも必要なセキュリティ対策とバックアップ
大事なデータのバックアップを取ったり、一元管理したりすることができるネットワークストレージのNAS。しかし、その大事なNAS内のデータがウィルスに感染することもありますし、ストレージの故障でデータが壊れてしまうかもしれません。そこで、NASにもセキュリティの設定や、バックアップが必要になるのです。
ここでは、NASにも必要となるセキュリティ設定や、バックアップの方法などについてご紹介しましょう。
NASでセキュリティ対策やウィルス対策が必要な理由
まず、NASを導入したら絶対にすべきなのが、セキュリティ対策とウィルス対策です。NASはファイル共有やバックアップを行うとういう特性上、社内などで使われる「大事なデータ」が保存されていることが多いはずです。しかし、搭載しているのが簡易OSであり、設定も簡単にできることから、セキュリティ対策やウィルス対策をしていないNASも多いようです。
ウィルス対策をしないNASは、OSやデータファイルが感染する場合もあります。もし、感染してしまった場合は、NASがウィルスの発信源となり、社内ネットワーク(LAN)内に甚大な被害をもたらしかねません。また、感染したデータが使えなくなることで、バックアップの意味をなさないケースも出てきます。
NASでキュリティ対策やウィルス対策をする方法
NASを選ぶ際は、ウィルス対策に優れたタイプを選ぶことも、検討すべき要素のひとつでしょう。
例えば、エレコムの「NSB-75S4DW6シリーズ」は、OSに「Windows Storage Server 2016」が搭載されています。Windows Storage Server2016は、「Windows Defender」を搭載しているため、ウィルス対策が可能です。

また、搭載OSがWindowsなので、ウィルス対策だけでなく、バックアップやログ監視などのアプリケーションソフトを使用することができます。
さらに、セキュリティワイヤースロットもありますので、物理的な盗難対策ができます。万が一盗難されたとしても、セキュリティ対策としてハードウェア暗号化を搭載していますので、暗号化しておけば利用者以外がデータを見ることは難しく、情報漏洩の可能性を最小限に抑えられるでしょう。
NASでバックアップが必要な理由とは?
NASは、データのファイル共有や一元管理、バックアップなどが目的ですから、社内の大事なデータを保存しているはずです。しかし、そのNASが壊れてしまえば、意味がありません。
バックアップストレージのバックアップを取るのは本末転倒のような気もしますが、NASもハードウェアである以上、経年劣化や自然災害など、何らかの理由で物理的に壊れてしまうことがあります。ですから、必ずバックアップ対策はすべきなのです。
また、たとえ新品でも、操作を誤ってデータを消してしまうこともあります。例えば、必要なデータを削除してしまったり、ファイルを上書きしてしまったりした場合でも、バックアップ(データの複製)があれば、その時点のデータからやり直しができるのです。これにより、データ消失のリスクを低減できます。
NASをバックアップする方法
前記したように、NASも必ずバックアップをするべきですが、どのような方法が良いのでしょうか。
最終的に何を選ぶかは、使用環境や予算等によりますが、ここではどのような方法があるのかをご紹介しましょう。
・リモートバックアップ
ネットワーク上で接続された2台のNASをメイン機とバックアップ機に分け、データをバックアップ保存します。このリモートバックアップには、即時バックアップする「リアルタイム」と、任意のスケジュールでバックアップする「スケジュール」という方法があります。もちろん、手動でタイミングを決めてバックアップをすることも可能です。
メイン機が故障した際は、バックアップ機の設定を変更し、メイン機として使用できます。
・ローカルバックアップ
1台のNAS内の共有フォルダ間や、NASのUSBポートに接続された外付けハードディスクにバックアップデータを保存するのが「ローカルバックアップ」です。これにより、NASが故障した場合でもデータ消失が防げます。
こちらも、リモートバックアップと同様に、即時バックアップする「リアルタイム」と、任意のスケジュールでバックアップする「スケジュール」があります。もちろん、手動でタイミングを決めてバックアップも可能です。
なお、ネットワーク経由で外付けハードディスクにアクセスできないようにしておけば、バックアップデータの改ざんや漏洩リスクを下げることができます。
・クラウドストレージ
クラウドストレージサービスを利用し、外部にバックアップデータを保存する方法です。上記2つのバックアップ先が社内に存在しているのに対し、クラウドストレージは物理的に離れた場所にありますから、停電や自然災害などのリスクヘッジに最適です。エレコムのNASなら、定評のあるクラウドストレージ「Amazon S3」を利用し、遠隔バックアップを行うこともできます。
・USBダイレクトコピー
一番お手軽なのが、USBデバイスを使ったダイレクトコピーです。エレコム製品の場合、USBポートにデバイスを接続し、NASの前面パネルから「USBコピー」ボタンを押すことで、コピーが実行されます。手動で行う必要があるため、手間はかかります。
そのほかトラブル対策
そのほかのトラブル対策としては、停電などの電源トラブルがあります。NASのバックアップをする理由のひとつに、突然の停電などでハードディスクに物理的な損傷を与えるリスクがあります。そこで、停電時の対策をする方法もあるのではないでしょうか。
もちろん、通常の状態では日本で停電することはまれです。しかし、落雷や地震など、自然災害などがあれば、その限りではありません。
停電対策としては、「無停電電源装置(UPS)」の導入が一般的ですので、万が一に備えたい場合は、購入を検討してみてください。