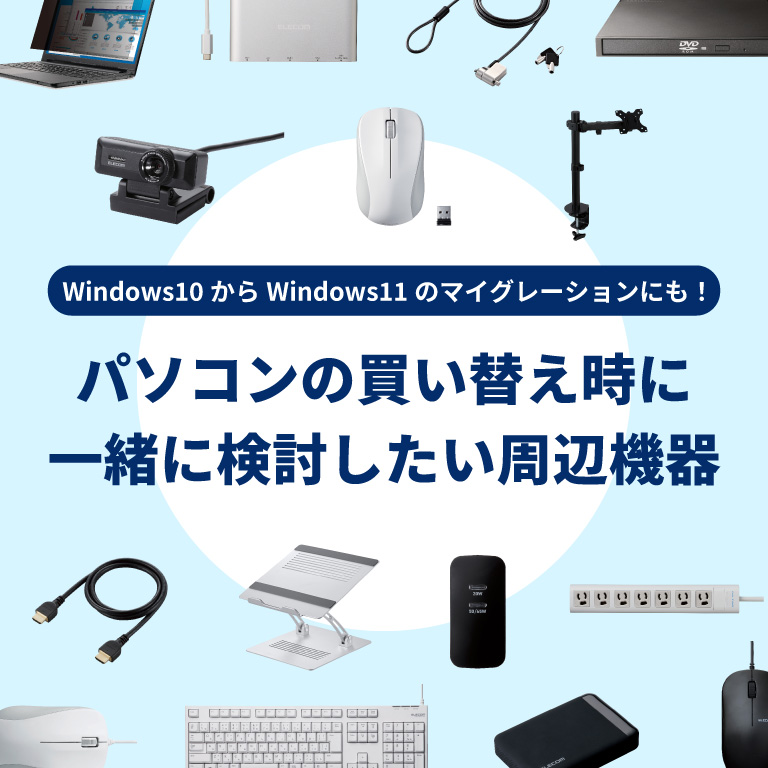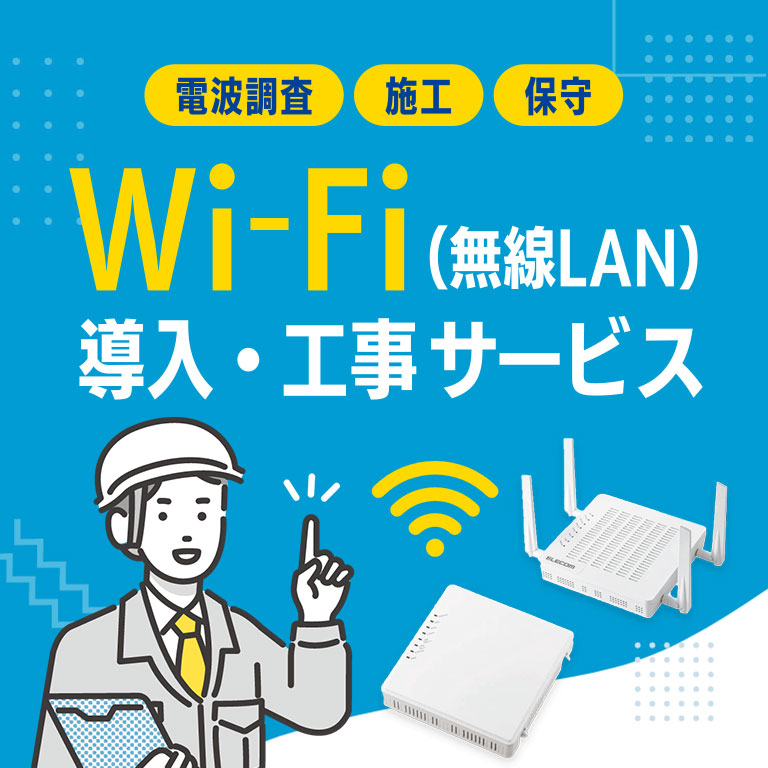- 概要
-
デジタルサイネージ。
名前を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか? 実は多くの場所で目にしているデジタルサイネージ。 今回は、デジタルサイネージとは何かやその基礎についてご説明します。
目次
デジタルサイネージとは
デジタルサイネージとは、簡単に言うと電子看板のことです。
街中や駅などで、画像がスライドしたり動画が流れたりする液晶ディスプレイやLEDの看板を見かけたことはないでしょうか?
そういった、電子機器を使って映像を表示する装置のことを「デジタルサイネージ」と呼びます。
-
デジタルサイネージの普及は広がりつつある
これまで駅やお店での情報発信ツールと言えば、看板・ポスター・チラシといったものが一般的でした。
しかし「電子看板」とも呼ばれるデジタルサイネージが誕生し、デジタル映像を用いることで多くの情報を手軽に発信可能となり、大きく注目されるようになりました。近年では街中や駅以外にも、大型ショッピングモール・ホテル・病院・イベントなどデジタルサイネージ利用に広がりが見られます。
またその機能・コンテンツもさまざまな種類のものが登場し、デジタルサイネージの市場規模は年々拡大していると言えるでしょう。
デジタルサイネージの活用方法

こちらでは、デジタルサイネージの活用方法についてご紹介しましょう。
-
販売促進のためのPRやブランディング
デジタルサイネージの活用方法として最も多いのが「プロモーション」への活用だとされています。
販売促進のためのPRや、企業価値を向上させるためのブランディングとして利用されます。これまでの広告といえばチラシ・ポスターなどの紙媒体が主流でしたが、最近ではデジタルサイネージを活用した情報発信がよく見られるようになりました。 幅広い分野での高い適用性や情報量の多さという特徴を活かし、人の目を引きつける広告としてさまざまな場所で利用されています。
-
情報発信や情報共有
上記のようなプロモーションだけでなく、人のニーズに沿った「情報発信・情報共有」といった活用方法もあります。
その日の天候情報や速報ニュースといった日常情報はもちろん、災害情報や行動に関するガイドラインなど緊急性の高い情報を配信することもできます。また、商業施設のガイドマップや観光向けの地域情報を発信する方法もあります。 社内向けに情報を共有する方法としても有効だと言えます。
デジタルサイネージの構成とは

デジタルサイネージを導入するという場合、ディスプレイ単体を用意すればすぐに始められるというわけではありません。 デジタルサイネージの基本的名構成としては、下記のようなものが挙げられます。
-
STB(セットトップボックス)
STB(セットトップボックス)は、コンテンツ内容をディスプレイに映し出す専用機材です。 HDMIケーブルを使ってディスプレイに接続する小型の箱です。
-
ディスプレイ
デジタルサイネージに使用されるディスプレイは一般的なテレビのディスプレイとは異なり、圧倒的な耐久性を持ち、屋外使用も可能なタイプのものです。 高輝度で高い視認性があるということも特徴の一つです。
-
デジタルサイネージソフトウェア(CMS)
デジタルサイネージソフトウェア(CMS)は、一般的にはコンテンツ管理を行います。 デジタルサイネージでは静止画・動画コンテンツを管理して、再生スケジュール設定も比較的簡単に行うことができるのです。
-
表示コンテンツ
ディスプレイに映し出される静止画・動画といった内容です。 資料作成ソフトを使ったテンプレートで簡単に作成できるもの、本格的な映像制作を行えるものまでさまざまなコンテンツが配信可能です。
デジタルサイネージの仕組み

デジタルサイネージの仕組みとしては、スタンドアローン型とネットワーク配信型の2つに分かれます。
-
スタンドアローン型のデジタルサイネージ
デジタルサイネージに外部接続もしくは内蔵されているメディアプレイヤーでUSBメモリやSDカードなどの記録媒体内のコンテンツを再生するのが、スタンドアローン型のデジタルサイネージです。
-
ネットワーク配信型のデジタルサイネージ
インターネット経由でコンテンツを受信し、再生するのがネットワーク配信型のデジタルサイネージです。 1店舗や1箇所で運用する際は、小回りの利くスタンドアローン型のデジタルサイネージの利用が適しています。
逆に、複数店舗など多くの場所で使用する場合には、ネットワーク配信型が適しています。 複数の場所で、同時にコンテンツの内容を変更することが可能です。
このように、使用するケースによって、適しているデジタルサイネージのタイプは異なるのです。
デジタルサイネージを選ぶ際のポイント

デジタルサイネージを実際に選ぶにあたって、設置するディスプレイの向きは縦型と横型どちらにするかということや、さまざまなディスプレイサイズの中からどのサイズを選ぶかということに悩まれる方は多いかと思います。
-
縦型・横型の特徴
縦型のディスプレイであれば、歩行者の目線と合わせることができるため、店舗の入り口付近に設置すれば看板の役割を果たしてくれるでしょう。
視認性が高く幅がそれほどない場所であっても設置可能なので、さまざまなシーンで活用することができます。横型のディスプレイであれば空白ができないので余白がなく、綺麗にコンテンツを表示させることができます。
設置の高さも気にすることなく、通路の壁やカウンター上にも設置することができるでしょう。
-
代表的なサイズは?
デジタルサイネージの代表的なサイズは、32インチ・42インチ・46インチ・55インチ・75インチです。
注意点としてはインチ数が同じ場合でも、画面サイズは異なることがあります。 「対角線の長さ=インチ数」なので、縦横の比率が変わってもインチ数は同じである場合があるのです。 そのためディスプレイサイズを検討する際には、「ディスプレイ画面の縦横の比率」と「インチ数」のどちらの数値も確認しておかなければなりません。販売されているディスプレイ画面の縦横比率の種類には、「4:3(スタンダードサイズ)」「16:9(ワイドサイズ)」があります。
現在の主流はワイドサイズであり、その中でも屋外でよく見られるデジタルサイネージのサイズは50インチ~75インチの縦型のものです。屋内に設置するという場合は40インチ~50インチのものが多く、店内のPOPなどに活用するという場合は10インチ~20インチの比較的小型のものがよく選ばれています。
屋外設置か屋内設置かによって活用の目的、設置の向きやサイズが異なってくるので、デジタルサイネージを導入する目的や活用法などは購入前に明確にしておくことが大切です。加えて、デジタルサイネージで発信する情報はどの範囲まで届くことを目的としているのかを考慮することも大切です。 それにより表示される文字サイズ・デザインなども変わってくるため、購入の際にはこの点にも着目しておけると良いでしょう。
デジタルサイネージ活用のメリット

デジタルサイネージの活用メリットとしては、以下のようなものがあります。
-
より多くの情報を伝えることができる
デジタルサイネージでは、動画の表示や複数の画像の切り替え表示をすることができます。 そのため、閲覧した人により多くの情報を伝えることが可能になります。 配信することのできる情報量が多いことから、より多くのことを伝えることができるのです。
-
コンテンツの出し分けが容易
スタンドアローン型では、USBなどメディアの差し替え。
ネットワーク配信型では、配信の設定。 などをすることで、時間帯や日別・天候などでコンテンツを出し分けることが容易にできます。ネットワーク配信型であれば、駅など、デジタルサイネージが複数設置されている場所でもすべてのデジタルサイネージのコンテンツを一括で変更することもできます。
-
人の目に留まりやすい
デジタルサイネージでは視認性が高いとされるディスプレイが使われることが多く、一般的な看板・広告などと比較すると、「人の目に留まりやすい」という特徴があります。 またデジタルサイネージの中では動画や音声を流すことのできるタイプのものもあり、動きや音をつけることで一層人の注意を引くことができます。
-
訴求対象者に合った情報を表示させることができる
「訴求対象者に合った情報を表示させることができる」という点もデジタルサイネージの大きなメリットであると言えます。 オンライン利用できるものであればディスプレイ表示を時間・場所・対象者に合わせて変更することができるため、より効率良く情報を周知させることができるのです。
デジタルサイネージ活用のデメリット

デジタルサイネージの活用デメリットとしては、以下のようなものがあります。
-
初期費用が多くかかる
紙の広告とは違って、ディスプレイやその環境設備など多くの初期費用がかかってしまうことは少しネックになるかもしれません。 しかしディスプレイの機能やメーカーによってその費用は異なってくるため、予算を気にしながらさまざまな製品を確認してみることが大切です。
-
故障する可能性もある
電子機器を利用する「デジタルサイネージ」は、故障する可能性があるという点もデメリットとして挙げられます。 特にディスプレイに関しては「衝撃を受けない・水がかからない」場所に設置する必要があります。 街中であれば多くの人が行き交う場所はそのような危険性も高くなるため、避けるようにするのが良いでしょう。
デジタルサイネージの活用事例

デジタルサイネージは、現在、駅などの公共施設やモールなどの商業施設、小売りの店舗など多くの場所で活用されています。
-
交通機関やモールでの活用
交通機関やモールなど多くの人通りのある場所では、広告として効果的に活用されています。 多くの人の目につくため、記憶にも残りやすいのです。
-
小売店での活用
小売店の入り口の立て看板、店頭のポップ。
などで、デジタルサイネージが活用されるケースも多いです。 店外であれば、天候や時間帯に合わせた情報を通行している人々に訴求し、店頭のポップでは、店内のお客さんたちにその日のセール品や売りたい商品の訴求などの情報を伝えることができます。 紙の看板やポップのように変更の手間もありません。 天候や状況の変化によってすぐに変更することができるのです。
-
モールなどの複合施設での活用
モールなどの複合施設では、広告だけでなく施設案内にデジタルサイネージが用いられることもあります。
タッチパネル式を設置することで、来店された人々が探しているお店に行きやすくなります。 来店された人々が自分たちから情報を探し出すことができるので、店舗・お客さん双方にとってメリットがあります。
-
スーパーマーケットでの活用
近年のスーパーマーケットでは生産者の状況・安全性に関して動画や画像で放映して、客足を落とさない工夫が施されて居るケースも多いのです。 「その野菜・果物がなぜ安全なのか?」という生産者による詳しい説明が目に見えて分かる ようにすることで、消費者を安心させることになるのです。
-
ウェディングホールでの活用
結婚式会場ではデジタルサイネージをウェルカムボード・サインボードとして利用することによって、画像を複数切り替えて使ったり、映像を流したりすることができます。
-
ホームセンターでの活用
数多くある商品棚から目当ての商品を見つけ出すことは非常に困難であり、従業員にとっても商品の把握具合・商品知識が異なるものです。 デジタルサイネージによって商品情報を各売り場に流すことで、特定の商品を見つけやすくなることにつながります。
-
飲食店での活用
昼・夜によって業態やメニューが違う飲食店の場合、時間帯ごとにデジタルサイネージのコンテンツが切り替わるようにしておくことでメニューの入れ替え手間やミスをなくすことができます。
-
工場・倉庫での活用
デジタルサイネージでその日のスケジュール・全体周知の事項などを発信することで、工場・倉庫内のすべての従業員に対して平等に情報を共有することができます。
-
イベント・展示会での活用
自社コンテンツをモニターで放映することで、展示スペースの広さに左右されず効果的にアピールすることが可能になります。 またデジタルサイネージを活用で、他店舗・企業との差別化を図ることができます。
-
ホテルでの活用
利用案内・館内マップなどの情報を配信することで、ホテルの施設内情報の共有がスムーズに行えます。 またデジタルサイネージをタッチパネル式のものにし、外国人利用者でも対応可能な多言語表示にするという方法もあります。
-
病院・クリニックでの活用
冬場のインフルエンザ・感染症予防法や夏場の熱中症対策など、その季節に合った情報を待ち時間中の患者さんに提供することができます。 また曜日・時間帯によって、患者さんの層に適した情報を変えていくことも効果的でしょう。
-
駅での活用
駅構内には、多くの情報が溢れています。 その中でも写真やイラストに動きをつけたり、映像を流したりといったことが可能であるデジタルサイネージは多くの人の目に留まりやすいと言われています。
-
オフィスでの活用
オフィス内のディスプレイにその日の業務内容に関する変更点やスケジュールといった情報を映し出すことにより、社員間での情報共有が簡単に行えます。 また天気予報・時事ニュースといったタイムリーな情報や、新入社員紹介・社内のイベント情報なども映し出すことで、社員同士でのコミュニケーションも円滑になることでしょう。
-
公共施設・役所での活用
デジタルサイネージを公共施設・役所のエントランスに設置し、施設フロアガイドとして活用されるケースもあります。 また、デジタルサイネージに整理番号を表示させておくことで、呼び出し案内やアナウンスが聞こえないという場合でも窓口対応をスムーズに受けられるよう設定しているところもあります。
-
学校・教育現場での活用
掲示板代わりとしてデジタルサイネージを活用し、セミナーやイベントへの告知を効果的に行う学校も増えています。 またサークルや作品の発表などが映し出されることもあり、学生同士のコミュニケーションを促すツールとしても効果的です。
インバウンドへの対応

日本に訪日外国人増えてきている中で、インバウンドマーケティングを実施し始めている事業者は多いと言います。 そしてデジタルサイネージは、そういった中で非常に有用だとされています。
たとえば「日本語が分からない...」という方にデジタルサイネージを用いて外国語で案内を行うことで、店員やスタッフとコミュニケーションをとることが難しいお客さんに対しても気負うことなく店舗を利用してもらうことができます。
そのほかの導入事例
小売業・製造業・医療法人・通信業などの分野でデジタルサイネージが導入され、生産性の向上や業務効率化につながったという事例もあります。
-
ある神社での導入事例
神社の中にある催事用の会食施設にて、ウイルス感染予防に対していち早く対応するためにデジタルサイネージとサーマルカメラが導入された例があります。
「3密」を防ぎながら体温測定ができる仕組みを実現し、安心して施設利用ができる環境を整えています。
-
ある介護施設での導入事例
介護施設でもウイルス感染予防策として、通所者の体温計測ができるサーマルカメラ、そして測定した体温を表示させるデジタルサイネージを導入したという例があります。 検温チェックが自動化され、感染対策として万全にアピールすることができるため、利用者も安心して施設利用が行えるのです。
デジタルサイネージは、このように多くの場所で活用されているのです。