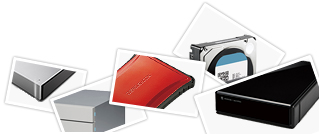
高速HDDは何が違う?その速度の違いの秘密に迫る
ハードディスク(HDD)は、円盤状の磁気ディスクにデータを保存することで、情報記録しておく記憶装置の一種です。パソコン向けのHDDの性能は通常、どれだけのデータを保存しておくことができるのかを表す「記憶容量」と、データの読み書きの速度に影響を与える「アクセス速度」の2つの基準で評価されます。どのような要因がアクセス速度に影響を及ぼすのか、内部の構造やしくみを少し覗いてみましょう。
HDDのアクセス速度を決めるおもな要因
HDDにおけるデータの読み書きは、まず磁気ディスクのデータを読み書きする場所に「ヘッド」が移動し、次にその場所で実際にデータを読み書きする、という2段階で行われます。
したがって、HDDにおけるアクセス速度は、以下の2つの動作時間の合計で決まります。
-
<HDDのアクセス速度に影響するもの>
- (1)読み出したいデータが記憶されている場所やデータを書き込む場所にヘッドを移動する時間
- (2)ヘッド移動が完了してから実際にデータを転送する時間
(1)はアクセス時間、(2)は(データ)転送時間と呼ばれています。必ずしも用語が統一されておらず、ここでいうアクセス速度のことをアクセス時間と表記したりする場合もありますが、考え方は変わりません。
それぞれの要因について、さらに詳しくご紹介します。
アクセス時間はシークタイムとディスク回転待ち時間で決まる
アクセス時間は、「ヘッドを目的の位置まで移動する『シークタイム』」と「ヘッドの位置までディスクが回転してくるまでの『ディスク回転待ち時間』」の2つの要因で決まります。ディスクの中心から外周(またはその逆)方向にヘッドを移動して、目的場所のディスクの周回にヘッドを持ってきて(シーク)、そのあとにディスクを回転させてヘッドの位置とディスクの位置を合わせます。
プラッターの回転速度と枚数がデータ転送時間に影響する
HDDの仕様には、多くの場合「7200rpm」などの回転速度が表記されています。rpmとは1分間あたりのディスクの回転数を表し、数字が大きくなるほど回転速度が高速になります。データの読み書きは、ディスクを回転させながら行いますので、回転速度が速ければ速いほどデータ転送速度が高速になります。
また、「プラッター」の枚数も転送速度に影響します。プラッターとは、HDD内に実際に存在する磁気ディスクのことです。プラッター枚数が少なく、プラッター1枚あたりの容量が大きいほうが、1回転で読み込めるデータ量が多くなります。したがって同じ回転速度の場合は、1枚あたりのプラッター容量が大きいほうが、データ転送速度が早くなります。
アクセス速度を決めるその他の要因
そのほかにも、HDDそのものの構造やしくみではありませんが、次のような要因がアクセス速度に影響を及ぼします。
キャッシュ容量
HDDは、データを書き込む際に一時的にデータを保存しておくキャッシュメモリを持っています。HDDのデータの書き込みは、ヘッドの移動やディスクの回転など物理的な動作を要するために、そのほかのPCのデータ処理速度に比べると低速です。その処理速度の緩衝地帯としてキャッシュメモリにデータを一時保管することで、PCやシステム全体の処理速度の低下を防ぐことができます。このキャッシュメモリの容量が大きくなれば、多くのデータを書き込む場合でも迅速に処理することができます。
PCとの接続インターフェース、USBバージョンによる速度差
HDDとPCとの接続方式は現在何通りかあり、その仕様やバージョンによってPCとHDD間の転送速度に差があります。
例えば、USBで接続する外付けHDDの場合は、対応するUSBのバージョンによってPCとHDD間のデータ転送速度に大きな差があります。USB3.0は転送速度が最大5Gbps(1秒間に5Gbit=500MBのデータを転送できる)です。USB2.0の転送速度が最大480Mbpsですので、約10倍高速でデータ転送をすることができます。また、USBの次期バージョンで、現在普及が進みつつあるUSB3.1 Gen2対応のUSB Type-Cの最大転送速度は、さらに高速な10Gbpsになります。