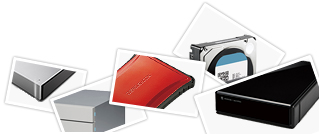
SSDの読み込みや書き込み速度が速くなるとどのような動作が速くなる?

SSDのメリットと聞かれれば、「パソコンが速くなる」という答えが多く返ってくるかもしれません。しかし正確にはパソコンが速くなるのではなく、データの読み込み速度や書き込み速度が速くなります。結果として、OSの起動時間が短くなったりするため、パソコンが速くなったように感じるのです。ここでは、SSDを使った場合に、どのようにパソコンのパフォーマンスがアップするのかをご紹介しましょう。
SSDがHDDより読み書きが速い理由

なぜSSDが速いかを検証するには、HDD、すなわちハードディスクとの仕組みの違いについて知る必要があります。
簡単に説明すれば、ハードディスクは磁気ディスクと磁気ヘッドを使って物理的に読み込みや書き込みを行います。SSDは磁気ディスクの代わりにNAND型フラッシュメモリに、電気的な処理でデータの読み書きを行います。
つまり、ハードディスクには物理的な動作がありますが、SSDにはありません。これが、SSDが高速にデータの読み書きができる理由なのです。
SSDで高速化できること

SSDが高速な理由はわかりましたが、実際にどのような動作が速くなるのでしょうか。ここでは、パソコンの起動ディスクにSSDを使った場合に、速くなる動作について確認していきましょう。
パソコンやアプリケーションの起動が速くなる
一番、恩恵を受けるのがパソコンの起動が速くなることでしょう。ハードディスクを起動ディスクに使った場合、OSが起動するまで1分を切ることはないと思います。しかし、SSDなら30秒前後で起動するのではないでしょうか。これは、OSの使用環境にもよりますが、少なくともハードディスクと比べてスピードの違いを顕著に体感できます。
また、インストールしているアプリケーションの起動時間も短くなります。PhotoshopやIllustratorなど、起動時間の長いアプリケーションを使う人にはメリットが大きいでしょう。
ハイバネーションからの復帰が速くなる
SSDの場合、ハイバネーション(休止状態)から復帰する際も、ハードディスクより速くなります。
理由は、ハイバネーション解除時にはハイバネーション時のデータをSSDに読み込むからです。このため、必然的にハードディスクよりも速くなります。
キャッシュの読み込みでブラウザの挙動が速くなる
あまり体感できないかもしれませんが、キャッシュがSSDに保存されているので、ブラウザの挙動が速くなる効果もあります。仮に、1ページ開くのに1秒速くなるだけだとしても、1日100ページ見れば100秒、1ヵ月で約50分速くなる計算です。

データの読み書きが速くなる
通常のデータファイルの読み書き、特に読み込み速度も速くなります。画像データなどを大量に扱いたいときにはたいへん便利です。書き込みも、ハードディスクに比べれば断然速いでしょう。
ですが、パソコンを使い続けることで、データファイルは肥大化していきます。SSDは容量に対する単価が高いので、データを大量に保存するには向いていません。また、容量不足が続くとアクセススピードが遅くなることもあります。可能であればOSのほか、主要なアプリケーションなど、起動回数の多いものだけをSSDに保存しましょう。
SSDが低速化した場合の原因と回避方法

高速なストレージとしてSSDを導入したものの、使っているうちに遅く感じるようになる場合もあります。単純にSSDのスピードに慣れてしまい、スピードを体感できないケースもありますが、何らかのトラブルで動作が遅くなっている可能性もあります。
ここでは、SSDが低速化してしまった場合の原因と回避方法についてご紹介しましょう。
容量不足による速度低下の場合
SSDは、空き容量が足りなくなった場合に、書き込み速度が低下してしまいます。これは、SSDのデータ保存の特性が原因です。
SSDは、データを保存する際、何もデータが保存されていない領域(空き領域)に保存します。これは、同じデータを上書きする場合も同じで、新規の領域に保存します(このとき、旧データはSSD上に残っているが、ユーザーからは見えない)。SSDを使い続ければ、いずれは空き領域がなくなります。
そのため、空き領域がなくなった場合は、書き込みを行う前に、一度使われていないデータ(過去に削除や上書きされたデータ)を削除して、空き領域を作ってから保存を行っているのです。
容量不足…つまり、SSDの領域で空き容量がなくなった場合は、書き込み前のデータ消去の時間がかかるため、速度低下の原因となります。
ハードディスクの場合は、使用されていないデータに直接上書きができますので、このようなことは起こりません。

トリム機能がオフになっている場合
前述した「容量不足による速度低下」は、実際にはあまり起こりません。それは、「トリム」と呼ばれる機能が、データを削除するときに未使用領域であることを「SSDコントローラー」に通知し、適宜、自動的に空き領域を確保するようにしているからです。
このトリム機能は通常は「オン」のはずですが、もし「オフ」になっていると、空き領域を自動で作ることはしません。そのため、空き領域がなければ、データを保存するたびに空き領域を確保する形となり、速度低下を起こすのです。
アライメントの調整に失敗している場合
別の可能性としては、「アライメント」の調整に失敗している可能性があります。アライメントとは、「ドライブのパーティションを作成する先頭位置(オフセット値)を最適化する」ことを指します。4096バイト(4K)単位でデータを書き込むSSDは、「4Kアライメント」となります。
このアライメントの調整に失敗していると、パーティション開始の位置が4096の倍数でなくなるため効率的な書き込みができなくなり、速度低下につながるのです。
AHCIモードではなくIDEモードになっている場合
古いOS(Windows 7など)から、Windows 10などにアップグレードした場合、Serial ATAの接続インターフェースをコントロールしているのが「IDEモード」のままである可能性があります。
IDEモードは、Serial ATA 1.0の時代に、IDEタイプのハードディスクとの互換性を重視したものです。しかし、SSD本来の能力を発揮するには、Serial ATA 2.5でサポートされた「AHCI(Advanced Host Controller Interface)モード」に変更する必要があるのです。古いOSからアップグレードをしたのであれば、注意したい項目のひとつです。
接続するSerial ATAのポートが間違っている場合
ユーザー自身でSSDを取り付けた場合、接続すべきSerial ATAのポートが間違っている場合があります。接続すべきSerial ATAのポートは「SATA 3.0ポート」で、「SATA 2.0ポート」ではありません。同じケーブルで接続できますし、接続すれば動いてしまうので間違ったことに気付かないで使い続けている可能性もあります。
SATA3の最大転送速度は6Gbpsで、SATA 2.0の最大転送速度は3Gbpsですから、その差は歴然でしょう。ただし、古いマザーボードの場合、接続しようにもSATA2ポートしかない場合もあります。

使用しているケーブルが劣化している場合
SSDとマザーボードを接続しているケーブルが劣化している場合も、SSDが本来のスピードを出せない原因となります。新しいハードを買っても、接続するケーブルは流用できるのであれば、そのまま使うケースも多いでしょう。
しかし、電気信号を送り続けている以上、ケーブルも劣化していきますので、長く使い続けるのは得策ではありません。また、ハードウェアと違って、ケーブルなどは「何でもいい」と安い物を購入している場合もあります。安いから悪いケーブルとは限りませんが、購入の際は注意しましょう。
SSDの能力が発揮できているかを確認しよう

SSDを導入することでデータの読み書きが速くなり、パソコンの動作が軽快になります。しかし、さまざまな要因でSSDのスピードが落ちたり、実は能力を発揮できていなかったりもします。
SSDは絶対に速いと妄信せず、ちょっとでも「おかしいな?」と思ったら、SSDの能力が発揮できているかを確認しましょう。