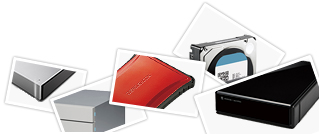
SSDを高速化する最適化設定とは?

SSDはハードディスクに比べて読み書きが速いことがメリットです。しかし、速度面でアドバンテージのあるSSDを使っていて、「前よりもパフォーマンスが悪い」と感じることがあるかもしれません。
このような場合、原因のひとつとしてSSDの空き容量不足が考えられます。ここでは、SSDを高速に使用し続けるために行いたい設定のほか、トリムについてご紹介しましょう。
設定変更で行うSSDの最適化

SSDを高速に使い続けるためにしたいことのひとつに、「容量不足を起こさないこと」があります。
仕組み上、SSDは空き容量が足りなくなった場合に、書き込み速度が低下してしまいます。ここでは、ファイルの保存場所やOSの設定を変更することでSSDを最適に使う方法をご紹介しましょう。
データファイルをハードディスクに移動させる
SSDの容量を圧迫する原因のひとつに、ユーザーのデータファイルが増えることがあります。特に、画像や動画などの大きいデータが増えると、容量の小さいSSDはすぐに容量不足となってしまうでしょう。
そこで行いたいのが、データファイルをSSD以外に保存することです。例えば、デスクトップパソコンであればハードディスクを増設したり、外付けのハードディスクを接続したりするのもいいでしょう。ノートパソコンであれば、ポータブル型の外付けハードディスクを追加して、データを持ち歩くことも可能です。
方法はさまざまですが、外付けのハードディスクを使えば、増え続けるデータから必要なデータを取捨選択して削除する手間が省けます。
OS以外のソフトウェアをハードディスクにインストールする
ユーザーが作成したデータだけでは空き容量が確保できない場合は、OS以外のソフトウェアを別のハードディスクなどにインストールして保存する方法があります。つまり、基本的にSSDは起動用のドライブと割り切り、OS以外のソフトウェアやデータファイルは、すべて別のハードディスクに保存するのです。
ただし、この方法はソフトウェアの起動時間を短くできるSSDのメリットを失います。ですから、よく使うソフトウェアだけはSSDにインストールしたままにするという手もあるでしょう。

仮想メモリの設定を無効にする
仮想メモリ機能も、SSDの容量を圧迫する可能性があります。仮想メモリとは、パソコン本体に物理的に内蔵されたメモリが不足した場合に、SSDやハードディスクなどのストレージをメモリとして利用する機能です。これにより、内蔵メモリの少ないパソコンでも、大きなデータを扱うことができます。
ですが、内蔵メモリが十分にあるのであれば、この設定を無効にしてもいいでしょう。反対に、内蔵メモリが十分になく、メモリ不足のアラートが出るようであれば、無効にするのはおすすめできません。
仮想メモリの無効化は、「システムのプロパティ」から行います。Windows 10の場合、「システムのプロパティ」を開くには、「スタートボタン」を右クリックし、メニューから「システム」を選択。次に、右側にある「関連設定」の「システム情報」を選択。最後に「システムの詳細設定」を選択すれば「システムのプロパティ」が開きます。後は「パフォーマンス」の「設定」をクリックし、「パフォーマンス オプション」の「詳細設定」タブで「変更」ボタンを押します。最後に、「仮想メモリ」で「すべてのドライブのページング ファイルサイズを自動的に管理する」のチェックボックスを外し、「ページング ファイルなし」のラジオボタンをオンにして、OKボタンを押せば設定完了です。ただし、設定後にパソコンを再起動しないと設定が有効になりませんので、ご注意ください。
ハイバネーションの設定を無効にする
仮想メモリと似た機能として、ハイバネーションがあります。ハイバネーションとはシャットダウン時に、メインメモリに残されていたデータを保存してくれる機能です。この機能が有効になっている場合、ハイバネーションをするたびにSSDにデータを保存し続けてしまいます。
ただし、この機能の設定は、コマンドプロンプトからコマンドを打ち込んで実行するため、難度が高めです。また、ノートパソコンは頻繁にスリープしますので、無効にしないほうが良いとの見方もあります。ですから、ハイバネーションの無効は最終手段のひとつとして考え、基本は有効のままにしたほうがいいでしょう。
OneDriveの設定を変更する
Microsoftのオンラインストレージである「OneDrive」は、インターネット上の専用ストレージにデータを保存できるサービスです。Windowsのセットアップ時に、サインアップのメッセージが出たことを覚えている人もいるでしょう。
このOneDriveを使っていなければ問題ありませんが、使っている場合は注意が必要です。このOneDriveは、オンラインストレージですが、初期設定では自分のパソコンにもデータが残っており、指定したフォルダ内のファイルを同期しているのです。そのため、OneDriveと同期するたびにSSDへの書き込みが発生してしまいます。
そこで行いたいのが、「OneDriveとの同期を停止する」ことです。Windows 10の場合は、「スタートメニュー」から「OneDrive」を選択し、開いたウインドウの左側から「OneDrive」を右クリックし、メニューから「設定」を選びます。次に「アカウント」から「このPCのリンクを解除」を選び、「アカウントのリンク解除」を選べば、OneDriveの同期を停止することができます。
再開したい場合は、再度OneDriveにサインインして、同期したいフォルダを選べば完了です。

SSDのデフラグやトリムは行うべきか?
ハードディスクのスピードが遅くなってきたときに、「デフラグ」という記憶領域を整理してきれいに配置する機能を使ったことがある人もいるでしょう。この機能は、Windowsが定期的に自動で行ったり、ユーザーが任意で行ったりすることができます。
しかし、デフラグはハードディスク向けの機能であるため、Windows 7以降のOSでは、SSDの自動デフラグは実行されません。代わりに、「トリム」と呼ばれるツールが自動実行され、SSDに保存されているデータがOS上、削除されている場合、記録されているデータを定期的に自動で削除しています。トリムは、基本的に必要に応じて自動的に行われるので、設定を変更する必要はないといえます。
ユーザーの使用環境に応じたSSD最適化を実践しよう
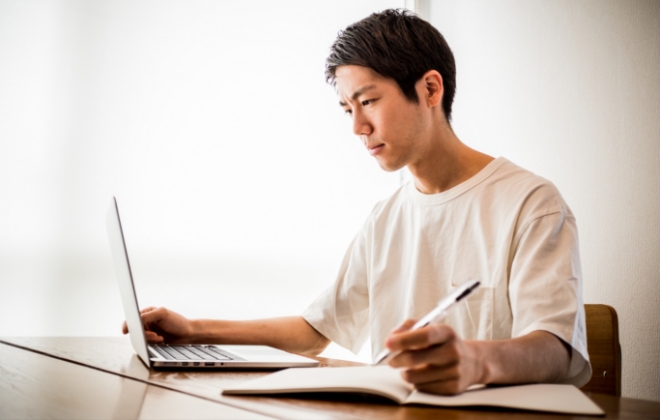
ご紹介したように、SSDを高速に使い続けるためには、いくつかの方法があります。しかし、これらはユーザー自身で設定変更などが必要なため、少々面倒に感じる人もいるでしょう。そのような場合は、フリーウエアなどでSSDの最適化を一括で行う方法もあります。ですが、あくまで自己責任で使用することになります。
これらを踏まえると、ユーザー自身の使用環境を考えて、必要な設定だけ行うのが最適な設定といえるのではないでしょうか。